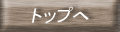仙巌園〜鉄製150ポンド砲〜
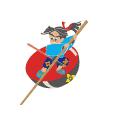

|
国指定名勝文化財 |
|
島津氏は、12世紀末、源頼朝から島津荘地頭職、薩摩・大隅・日向3ヶ国の守護職に任命された惟宗忠久が、島津を名乗ったことにはじまります。 江戸時代になると、島津氏は、琉球の支配も認められ、72万石の外様大名として南九州を統治し続けました。 磯庭園は正式名称を仙巌園といい、万治元年(1658年)、十九代島津光久が鎌田出雲政近の大磯下津浜門屋敷を御用地と成し、御仮屋を建てたのが始まりとされています。島津藩ではすでに十八代島津家久が城山に鶴丸城を建て、島津氏の居城としており、仙巌園に建てられた御殿は、島津家の別邸として代々の藩主に受け継がれました。 江戸時代中期、二十一代吉貴の代には、中国より江南竹が移植され、曲水の庭が作庭されたと伝わっています。また、二十七代の斉興(なりおき)の代には、庭地拡張が行われ、同時に千尋巌、集仙台、筆塚なとが造られました。さらに廃藩置県後には二十九代の忠義が移り住み、正門が造られ、ほぼ現在の形に整えられました。 なお、この仙巌園は、昭和33年(1958年)に、名勝として国の文化財に指定されています。 |
|
明治7年(1874年)、城山の鶴丸城は焼失。以後再建されることはなかったそうだ。 |

|
西欧列強が東アジアに進出した19世紀、28代島津斉彬は防衛のために西洋式の反射炉や溶鉱炉・鑚開台を建設し、鉄製大砲を製造しました。斉彬の側近市木四郎は、薩摩藩は安政4年(1857年)に鉄製150ポンド砲の製造に成功したと記しています。文久3年(1863年)、薩英戦争の時、鹿児島城下には2門の150ポンド砲があり、威力を発揮しました。 |



|
昭和4年(1929年)7月23日、与謝野鉄幹・晶子夫妻は磯庭園を訪れている。 |
|
磯の島津公爵邸にて。 いにしへの太守の庭に海を見て佇むこころのどかなるかな
『霧島の歌』(其一)
三州の大守の磯の林泉にひぐらしめきて鳴れる水かな 渓川は磯の御館の水門をくぐらんとして白波を上ぐ
『霧島の歌』(其二) |
|
昭和14年(1939年)10月、斎藤茂吉は磯庭園を訪れている。 |
|
磯島津邸 たかむらは青き光を放つとぞ知りぬるわれはしばし離れつ あるときは潮の波も照りかへすここのみ園の石のうへのつゆ
『のぼり路』 |
|
昭和43年(1968年)、水原秋桜子は磯公園を訪れた。 |
|
磯公園 薫風の床几火山灰(よな)降るぢやんぼ餅
『殉教』 |