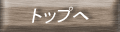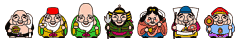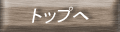小林一茶ゆかりの地
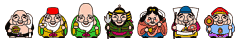
『西国紀行』
寛政7年(1795年)1月8日、一茶は讃岐から伊予に向かい、15日、松山の栗田樗堂を訪ねた。
乙卯歳旦
於専念精舎
今日立春向寺門 々々花開愈清暾
入来親友酌樽酒 豈思是異居古園
元日やさらに旅宿とおもほへ(え)ず
土居、島屋と云はたごやに宿。八里也。人々は金比邏参とて相宿のすだく〔に〕つけても、君が世のありがたさは、きのふや今日までは松かざりのありしが はや、
出て見れば我のみならず初旅寝
十日、二里半ほど、新浜、騎龍亭に泊。
帳閉(とづ)る加勢もせずに旅寝とは
十一日、八里程と覚。中村と云所に泊る。
十二日、四里、今治、卯七を訪ふに、公のさはりあれば、又半道、波止浜、花雀亭に宿。
御出肆ながら春宵千金ぞ
十三日、槌(樋)口村などいへる所を過て、七里となん、風早難波村、茶来を尋ね訪ひけるに、已に十五年迹に死き〔と〕や。後住最明寺宿リ乞に不許。前路三百里、只かれをちからに来つるなれば、たよるべきよすがもなく、野もせ庭もせをたどりて、
朧々ふめば水なりまよひ道
百歩ほどにして五井を尋当て、やすやすと宿りて、
月朧よき門探り当たるぞ
十四日、十丁程、八反地村、兎文に泊る。
門前や何万石の遠がすみ
歌仙満巻して、
十五日、松山二畳庵に到る。
魚文かたに、素堂・芭蕉翁・其角の三福対のあれば、訪ふ(う)て拝す。
正風の三尊見たり梅の宿
累日風交して、探題、
猫飼ずば罪作らじを雀の子
春の雨倦もはてなで糸車
二月朔日を小正月と云て、雑煮の仕納となん、此地のならひ也。
召仕新しき哉小正月
道後温泉の辺りにて
寝ころんで蝶泊らせる外湯哉
五日、松山を出て三里、三津浜方十亭を主とす。
九日、人々と共に小深里の洗心庵に会。前文略。
汲みて知るぬるみに昔なつかしや
十九日、波止浜を出て六里、中村に泊る。明日、村より十丁程、実報寺の桜見にまかるに、今を盛なれば、壱樹(ひとき)ざくらと云。
遠山と見しは是也花一木
並桜遥拝す人をてらす哉
廿日 四里、大町はたごやに泊る
廿一日 雨、逗留のつれづれに昼寐して
起て見れば春雨はれず日も暮れず
桃の明スサ切男眠気也
廿二日 伊曽野、都英子と折から雨後のさくらのちりぢりなる神社に参りて、
拝上頭に花の雫かな
四里 津のあみだ堂に泊る
廿四日、半道程田上影香舎に泊る
長閑や雨後の縄ばり庭雀
九日、藤戸、天柄木などいへる所を過て、備前岡山に至ル。此地に風流好るものゝありといへ共、派違なれば尋ねず、城下一里離れて、二本松に泊。
十七日、明石より兵ごの道連あれば、夜道して、同行二人、頻に眠気催れば、軒をかりて、
笠の露眠むらんとすれば犬の声
寛政7年(1795年)3月27日、一茶は四天王寺に詣で句を詠んでいる。
小林一茶ゆかりの地に戻る