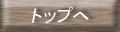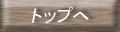2008年〜山 梨〜
昇仙峡〜仙娥滝〜

グリーンライン昇仙峡から遊歩道を歩く。

昭和5年(1930年)、富安風生は昇仙峡を訪れている。
昇仙峡 二句
岩の上に傘を杖つく紅葉かな
紅葉溪月をかかげて暗きかな
『草の花』
羅漢寺橋

昭和8年(1933年)10月21日、与謝野寛・晶子夫妻は昇仙峡を訪れている。
羅漢寺の新緑

覚円峰

花崗岩が風化水食をうけてできたもので、急峻で直立約180メートルあり、この峡中奇勝の最たるものである。この岩頭に澤庵禅師の弟子覚円が座禅を組んだといわれ、覚円峰と呼ばれている。
甲府市
雲飛ぶや天馳使(あまはせづかひ) が種置ける覚圓峰の岩肩の松
『馬酔木』(明治39年2月15日)「御嶽乃歌會」に「明治三十九年一月、此の重々しき新年の初頭、明けて七日といふ日を以て、吾々は甲州御嶽の峡中に於て歌會を開けり、」とある。
川なみがあらふ岩よりたかければ霧の拭へり覺圓峰
「いぬあじさゐ」
天狗岩

ことごとく空に入りたる岩山を見上ぐる渓の路は三尺
『与謝野寛遺稿歌集』
石門

石門と人うぃしふれどたそがれて渓に思ひぬ雲の一つと
『与謝野寛遺稿歌集』
昇仙峡の渓流

明治42年(1909年)4月25日、河東碧梧桐は荻原井泉水・大須賀乙字らと共に昇仙峡を訪れた。
四月二十五日。晴。
全長一里に亘る昇仙橋の気色は、序破急の順序の如何にも整然たるものであると思う。鷲巣岩の序に始まって、覚円峰の破に及び、光景次第に急を告げて、終に仙娥滝の奇を現出する。脇僧と老翁の対立、ついに獅子の舞い込みに終るが如くである。仙娥滝は一天斧を加えた如き巨岩の狭窄の間を三段に落る。無形の漏斗に絞られた水は、ただ虎口を逃れた様に沫(しぶき)と飛び霧と散ずる。そうして、その水を圧した岩の一方の鑿壁は、巍々として蒼穹を摩して立つ。また一奇瀑たるを失わぬ。
岩を割く樹もある宮居躑躅かな
昇仙橋即詠の内一句
滝に景は尽きたれど躑躅奥ありて
仙娥滝

渓の路仙娥の滝にきはまらず亭の待つありそのうへの山
『与謝野寛遺稿歌集』
仙娥滝は日本の滝100選のひとつ。
地殻の断層によってできた。高さ30mの壮麗な滝は新緑から紅葉、雪景色と四季にその美しさを装います。
昭和14年(1939年)、水原秋桜子は昇仙峡を訪れている。
昇仙峡
岨に生ひ秋渓(しゅうけい)に伏すも松ばかり
秋山(しゅうざん)はめぐり幾瀬のこもり鳴る
瀧津瀬にさしいでし松の秋日和
鶺鴒のひるがへり入る松青し
櫨紅葉激湍(げきたん)左右に落つるところ
懸巣鳴き渓声道をやゝ離る
紅葉舞ひ仔馬が炭を負ひくだる
『蘆刈』
湯村温泉へ。
2008年〜山 梨〜