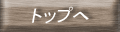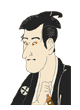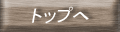2015年〜奈 良〜
竹内街道〜綿弓塚〜
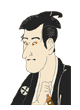
葛城市竹内の国道166号は竹内街道である。

竹内街道の旧道に「芭蕉ゆかりの綿弓塚」があった。

竹内街道
推古天皇21年(613年)に、難波と飛鳥京の間におかれたこの街道は、飛鳥時代にわが国最初の官道として栄え、大陸からの文物を大和飛鳥にもたらしました。峠の東北にある万歳山城などの中世の城塁址はこのあたりを駆けめぐった大和武士たちの夢を偲ばせています。中・近世には、伊勢、長谷参詣が隆盛し、茶屋、旅籠が峠を行く人々の旅情を慰めました。竹内街道の風景には多くの文化人たちが筆を取り、貞享5年に松尾芭蕉が河内に向かい、幕末嘉永6年に吉田松陰が竹内峠を経て儒者を訪ね、文久3年には天誅組の中山忠光等7名が志果たせぬままここに逃走しています。
綿弓塚

右側面に芭蕉の句が刻まれている。
綿弓や琵琶に慰む竹の奥
大和の国に行脚して、葛下(かつげ)の郡竹の内と云処は彼ちりが旧里なれば、日ごろとゞまりて足を休む。
芭蕉旧跡 綿弓塚
この句碑は、『野ざらし紀行』に「綿弓や琵琶に慰む竹の奥」とあり、この時の好句を記念するため、芭蕉の歿後115年を経た、文化6年(1809年)10月に建てられたものである。
この地は、芭蕉の門人千里の郷里で、芭蕉は貞享元年(1684年)秋千里の案内でこの地に来り、数日間竹の内興善庵に滞在している。さらに元禄元年(1689年)春再びこの地を訪れ、孝女伊麻に会って、その親を思う美しい心にこの上もなく感激し、「よろづのたつときも、伊麻を見るまでのことにこそあなれ」と友人に手紙を送っている。俳聖芭蕉は貞享元年秋、元禄元年春その他数回当地を訪れたと思われ、数々の句文を残している。
当地方で詠まれた句
|
|
綿弓や琵琶に慰む竹の奥
| (秋 竹内 甲子吟行)
|
|
木の葉散桜は軽し桧木笠
| (秋 吉野 真 蹟)
|
|
里人は稲に歌よむ都かな
| (秋 竹内 真 蹟)
|
|
楽しさや青田に涼む水の音
| (夏 竹内 真 蹟)
|
|
世に匂ひ梅花一枝のみそさざい
| (春 竹内 夏炉一路)
|
|
初春先づ酒に梅売るにほひかな
| (春 竹内 真 蹟)
|
|
冬知らぬ宿や籾摺る音霰
| (冬 長尾 夏炉一路)
|
|
僧朝顔いく死かへる法の松
| (秋 當麻寺 甲子吟行) |
千里の句碑もあった。

深川や芭蕉を富士に預け行く
何某ちりと云けるは、此たびみちのたすけとなりて、萬いたはり心を盡し侍る。常に莫逆の交ふかく、朋友信有哉此人。
寛政7年(1796年)4月、小林一茶が竹内峠から大和三山を俯瞰して句を詠んでいるそうだ。
空見つ倭の名処一見せばやと、河内の国ゆ山ごえしてやす
らふ折から、此国中眼下にみゆれば、忽炎日の眠気散じて
遠かたや青田のうへの三の山
嘉永6年(1853年)4月4日、吉田松陰は大阪から竹内峠を経て八木の儒者谷三山を訪ねている。
四日、晴、発大阪、將抵八木訪谷三山翁、従坂赴八木、道踰田尻嶺爲便、余不詳地理、越竹内嶺、至高田、日已暮矣、此至八木一里、是日、行程九里、
2015年〜奈 良〜に戻る