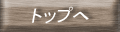2006年〜長 野〜
梅松寺〜一茶の句碑〜

小布施の梅松寺が一茶ゆかりの寺だということで、行ってみた。

梅松寺は小布施町の六川にある。
小林一茶は文化10年六川村を訪れて以来、たびたび当寺を訪れ、句会などを開き、小布施地域の門人の俳諧指導にあたった。
文化6年(1809年)7月30日、一茶は六川村の知洞上人の事を書いている。
卅日 晴 六川知洞上人中食 長沼ニ入
『文化五・六年句日記』
文化10年(1813年)2月22日、一茶は六川村を訪れた。
廿二 晴 六川ニ入
『七番日記』(文化10年2月)
六川大庄屋寺島夏焦(8代善兵衛)を訪れたのである。
これが初めてというわけではないであろう。
同年4月18日、一茶は渋温泉から六川村を訪れる。
十八 晴 六川ニ入
『七番日記』(文化10年4月)
同年6月4日、一茶は六川村を訪れている。
四 晴 六川ニ入 夜大雨
『七番日記』(文化10年6月)
同年閏11月23日、一茶は六川に入る。
廿三 晴 六川ニ入 大綾在所越後国母去十七日ニ没
『七番日記』(文化10年閏11月)
文化11年(1814年)2月11日、湯田中から六川の梅松寺へ。
十一 晴 六川梅松寺
『七番日記』(文化11年2月)
同年6月2日、一茶は梅松寺の住職知洞と湯田中に入り、9日門人久保田春耕がいる高山村の紫へ、11日には知洞のいる六川村に入る。
二 晴 知洞ト田中ニ入
|
|
九 晴 紫ニ入
|
|
十一 晴 六川ニ入
|
『七番日記』(文化11年6月)
文化12年(1815年)5月10日、湯田中から六川村を訪れる。
文化15年(1818年)2月5日、一茶は湯田中に入る。9日、湯本希杖と常楽禅寺に詣で、六川へ。
五 晴 素玩ト田中ニ入
|
|
九 晴 希杖ト中野常楽禅寺詣
|
無相(窓)国師坐禅石山ニ西国卅四番石観音
|
六川ニ入
|
当寺の住職は当山十九世弘圓和尚で、雅号を独楽坊知洞といい、詩歌をたしなみ、一茶の門人で、俳諧にすぐれていた。
梅松寺の前に一茶の句碑があった。

真丸に芝青ませて夕涼
出典は『七番日記』。文化13年6月の句である。
文化13年(1816年)6月13日、一茶は菅相山梅松寺に入る。