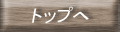『花入塚』(青梔編)

俳 書
『花入塚』(青梔編)


| 明和7年(1770年)10月12日、竹鸞台風徐・雪渕楼野菱序。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安永5年(1776年)1月、蓬生庵青梔自跋。 |
| 哥仙行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちよりて花入探れんめ椿 | 翁 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降こむまゝの初雪の里 | 彫棠 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目にたゝぬつまり肴を引替て | 晋子 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽織のよさに行を繕ふ | 黄山 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕月の道ふさけなり鉋屑 | 桃隣 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出代過て秋そ世話しき | 銀杏 |
| 石塔供養 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咲かえる花をそれとも塚供養 | 野菱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小春の空の虚実明らか | 青梔 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらから詣ふへき筈の人見えて | 風徐 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砥の目も久しふりの庖丁 | 芦牛 |
| 諸国名録 |
||
| 明日の事は明日にして咲く木槿哉 | 美濃北方 | 帰童仙 |
| 春中の仕事に延る柳哉 | 伊勢桑名 | 無三 |
| 花さかり雨も大事に降りにけり | 仝山田 | 麦浪 |
| 及はれぬ手をあちらから藤の花 | 出羽 | 風伍 |
| 菊の日や誰か忘れて垣に杖 | 越後堀之内 | 徐々 |
| さひしさもおかしさも尾に鶉かな | 仝新発田 | 許虹 |
| 夕くれの見世覗きして団扇哉 | 既白 |
|
| 思ひきつて細脛ぬかせ御祓川 | 松後 |
|
| 朝顔や今朝焚くものに這かゝり | 常陸水戸 | 三日坊 |