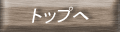天田愚庵邸〜天田愚庵像〜
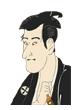


|
天田五郎は、明治20年出家、法名は鉄眼と称した。34歳であった。 明治25年春、京都・清水寺に登る産寧坂に庵を結び、庵室も自分も「愚庵」と称した。ここを正岡子規と高浜虚子が訪ねたのは、11月のことであった。 明治26年、元養父・清水次郎長の死去もあり、かねてからの念願であった父母菩提と衆生結縁のため、秋の彼岸入り日・9月20日に、西国三十三ヶ所巡礼の旅に出た。この立像は、その時の姿そのものである。道順は、先ず伊勢神宮と熊野三社に参詣、その後は番号順に三十三ヶ所の霊場を巡った。 12月21日・冬至の日、93日の旅を終え、無事帰庵した。里程約400余里に及ぶ巡礼の旅であった。 「順礼日記」はこの時のもので、漢詩26篇、和歌33を含め名文で綴られ、「明治の奥の細道」と称賛されている。
(作者‥日展会友 小滝勝平氏) |
|
十一月。子規、『日本新聞』入社。家族を迎へる為め西下の途次、 共に嵐山に遊び大堰に舟を浮ぶ。愚庵子を東山の草庵に訪ふ。 |

|
天田愚庵は安政元年(1854年)7月20日、磐城平藩主安藤信正の家臣甘田平太夫の五男として平城下に生まれた。幼名を久五郎といい、後に(明治4年)天田五郎と改めた。 明治元年(1868年)、15歳で戊辰の役に出陣中、父母妹が行方不明となる。以後20年間、肉親を捜して全国を歩った。その間、山岡鉄舟の知遇を受け、また一時、清水次郎長(山本長五郎)の養子となった。この時期「東海遊侠伝」を出版、その後の「次郎長もの」の種本となっている。 明治20年、五郎34歳のとき滴水禅師によって仏門に入り、鉄眼と号した。 明治25年、京都清水に庵を結んで「愚庵」を名乗った。漢詩において異彩を放ったばかりでなく、万葉調歌人としてすぐれ、正岡子規に大きな影響を与えた。 明治37年(1904年)1月17日、京都伏見桃山の庵で没した。享年51歳。その旧居は昭和41年秋、有志により伏見桃山からここに移築復元された。 平成元年11月
いわき市教育委員会 |

|
明治30年、京都・産寧坂の愚庵の庵に長いこと滞在した桂湖村が帰郷する時、園中の柿(つりがね)15顆と松茸を彼に託して、子規の病床に届けた。 その時、子規は俳句をものし、礼状と共に届けようとしたが、投函が遅れた。愚庵は、子規からの便りのないことを怪しんで、湖村への便りに次の一首を加えた。 まさをかは まさきくてあるか かきのみの あまきともいはず しぶきともいはず 湖村は、これを子規に示した。子規は早速愚庵宛に書簡を書いた。この内容は、まず愚庵の歌について、ひときわ目立っていることをうらやましく思うと評価し、6首の歌を書き送った。これは、子規の従来の歌とは明瞭に、一線を画し得るもので、歌人の産声とも聞こえるものである。 みほとけに そなえし柿の あまりつらん 我にぞたびし 十あまり五つ 柿の実の あまきもありぬ かきのみの 渋きもありぬ しぶきぞうまき 2首のみをあげたが、子規の短歌への移行が明らかで、一つの契機と捉えることが出来る。 産寧坂・愚庵の柿の木は既にない。この木のいわれを絶やさぬため、実生して育てられたのがこの柿の木で、中柴邸(平・仲間町)より移植したものである。 これをご覧になり、愚庵と子規の関係や、子規が短歌革新を進めるに至った経緯を想起して頂ければ幸いであります。 |



| 清水港の宿りにて 愚庵詠 |
| せこやこひし勢子や戀しとおもふより夢に入りしかあはれ我妹子 |