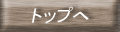隣船寺〜種田山頭火の句碑〜
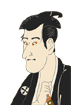
|
昭和7年(1932年)1月6日、種田山頭火は隣船寺の宗俊和尚を訪ねている。 |
|
水といつしよに歩いてゐさへすれば、おのづから神湊へ出た、俊和尚を訪ねる、不在、奥さんもお留守、それでもあがりこんで女中さん相手に話してゐるうちに奥さんだけは帰つて来られた、遠慮なく泊る。 |

|
昭和7年(1932年)4月18日、種田山頭火は隣船寺の宗俊和尚を訪ねている。 |
|
今夜は俊和尚の典座だ、飯頭であり、燗頭であつた、ふらん草のおひたし、山蕗の甘煮、蕨の味噌汁、みんなおいしかつた、おいしく食べてぐつすり寝た。
かういふ手紙を書いた、それほど俊和尚はなつかしい人間だ。―― |
|
また松のお寺の客となりました、俊禅師貎下の御親酌には恐入りました、サービス百パーセント、但しノンチツプ、折から庭の桜も満開、波音も悪くありません。…… |

|
自由律俳句「層雲」の同人で、全国を行脚しながら独特のすぐれた作品を世に出した、漂泊の俳人種田山頭火(1882〜1940)と深い親交のあった当寺第十六世田代宗俊和尚が、昭和8年の秋に全国で最初に建立し、山頭火自身が、この句碑の為に揮毫した唯一の生前句碑である。 山頭火がこの寺を訪れた当時の境内には「潜龍松」と呼ばれる老松が四方に枝をのばしていた。 向かい側には今も地元の人々に信仰の篤い観音堂があり、山頭火の出家の地でもある味取観音での句が選ばれた。文字の彫刻は、地元の石工によるものだが、非常によく筆跡を表しており、又碑石は、不用になった墓石の裏面を生かして使われた事など、いかにも山頭火にふさわしい句碑として広く親しまれている。 |
|
昭和15年(1940年)5月31日、種田山頭火は八幡の鏡子居から神湊の隣船寺へ。 |
|
午後出立、黒崎まで電車、そこから汽車で赤間まで、さらにそこからバスで神湊へ、隣船寺拝登、俊和尚と握手して、しばらくしばらく。 前の宿屋に案内されてもてなされる、すまないと思ひつゝも食べた食べた、飲んだ飲んだ、おいしかつたおいしかつた。 ならんで寝床にはいつたが、私だけはいつまでもねむれなかつた。 神湊海岸 砂にあしあとのどこまでつづく 晴れるほどに曇るほどに波のたはむれ
『松山日記』 |
|
昭和15年(1940年)10月11日、山頭火は松山の一草庵で死去。 昭和16年(1941年)3月21日、一草庵に山頭火2番目の句碑が建てられた。 |



|
「魚屋旅館」の中庭に種田山頭火「晴れるほどにくもるほどに波のたわむれ」の句碑があるはずだが、「魚屋旅館」は廃業。 |