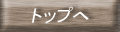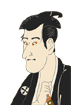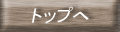江戸時代後期の狂歌師太田南畝(蜀山人)は「坂を下るに赤土の岸(がけ)あり。松の並木をゆくゆく坂を上り下りて又坂を下りゆけば、左に黒崎の内海(洞海湾)見ゆ。」とその紀行文(小春紀行)に、このあたりの様子を記しています。
この松並木は幕府が全国の街道に松や杉を植樹させた名残で、黒崎から木屋瀬にかけて昭和20年ごろまでは多くの松を残していましたが、今はわずかにこのあたりが昔日の長崎街道の面影をとどめているのみです。昭和30年代には街道松は57本ありましたが、昔の松は現在2本を残すのみとなっています。
なお、北九州市指定史跡範囲は旧街道緑地の一部(幅20〜30メートル、長さ約310メートル、面積約8,000㎡)です。
平成11年(1999年)の台風で倒れ枯死した松は、樹齢推定143年で、その根株は、江戸〜平成の5つの時代を生き抜いた松として保存されています。
|
夕陽を浴びた松並木

寛永10年(1633年)9月28日、西山宗因は熊本から上京の途上、黒崎に到る。
|
廿八日、筑前の国黒崎の津にいたりぬ。是までをくりし人をかへすとて、此比の口ずさびどもかきつけてやりき。
「肥後道記」 |
明和8年(1771年)5月4日、蝶夢は小倉から黒崎を経て直方へ。
|
黒崎ははや筑前の国なり。そのかみ伊予掾純友兄弟のこもりし所か。木屋の瀬より川づらにそひて行ば、直方にいたる。文紗といふ人の別業にやどる。
|
文化2年(1805年)10月15日、太田南畝は黒崎宿に着く。
|
石橋二ッわたりて人家あり黒崎といふ。さし入に土塀あり、宿の右に鳥居ありて岡田宮といふ額あり。神武天皇をまつるといふ。
|
嘉永3年(1850年)8月29日、吉田松陰は長崎に遊学する途中で黒崎宿に泊っている。
|
豐筑の境に至れば、道右に一石柱あり、是れより東、豐前國小倉領の由刻す。道左に大石柱あり、是れより西、筑前國の由刻す。行くこと一里餘にして黒崎に宿す。内裡より此迄四里半、熱氣未だ全く解せず、且つ木屋瀬迄三里許りを行かば日没せんことを恐れ、七ツ時此に宿す。
|
2017年〜福 岡〜に戻る