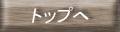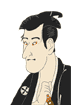
鵜坂神社〜延喜式内社〜


|
本神社は延喜式内の大社で、第十代崇神天皇の御代北陸道将軍大彦命の勧請により創建。白雉年間(7世紀後半)堂宇再建、さらに称徳天皇の御代僧行基が勅を奉じて二十四堂伽藍を建立。越の総社として年中七十二度神事が行われた。 歴朝の崇敬も厚く貞観9年(9世紀後半)には神階従三位に上がり(三代実録)白河、堀川天皇(11世紀末)の御代には御卜奏により中祓いを科せられた(朝野群載)。治承3年(12世紀末)源義仲の兵火により焼失したが、源頼朝が再建し鵜坂、鵜坂新、有沢、庄高田、下野、久郷、分田、島黒瀬、高田新、高田の十ニケ村を社領とし神階正一位に進めたという。 その後、上杉謙信の兵火や神通川の水災などにより往時の盛観を失ったが、往古の神徳の高さから、明治6年社格制により県社に列せられ、大正4年鵜坂地区19社が合祀し現在の鵜坂神社となった。 ◆御祭神 主神 面足尊(おもだるのかみ )・惶根尊(かしこねのかみ )/神代六代の祖神、国土造成、人間の形成の祖神 相殿 鵜坂姉姫神・鵜坂妻姫神/郷土開拓の神、婦負郡発祥の女親神 亦大彦命/北陸、越の国の開拓、農耕の祖神 ◆御神徳 御祭神の御神徳から、殖産興業・商売繁盛・交通安全・学業成就の守護神として仰ぎ、また笞祭(尻打祭)の縁起により縁組安産の守り神様として親しまれている。 ◆尻打祭 本神社には平安朝頃から尻打祭が行われていた。この祭りは婦女の貞操を戒めた祭りとして日本五大奇祭の一つとして全国に有名を馳せていたが、この神事の根因は増産や縁組、安産の祈りであってと推察される。明治以降、雌馬により神事が行われていたが、第二次大戦以後途絶えている。 いかにせん 鵜坂の森に 身はすとも 君が苔の数ならぬ身を 俊頼 油断して 行くな鵜坂の 尻打祭 芭蕉 あなこわや 鵜坂祭の 音にむち 其角 ◆鵜坂寺 奈良時代より神仏習合の風習が広がり、名神大社には別当寺を置き社僧を配した。本神社では称徳期に僧行基が勅を奉じて二十四堂伽藍を建立するなど隆盛を誇ったが、その後後数次の災禍に遭い衰微し、明治3年廃仏棄釈により鵜坂寺は第七十五世観美で廃絶、今は僅かに境内の一部に往時の面影を偲ぶのみである。 ◆大伴家持の歌碑 天平20年越中国司家持は、越中の大社鵜坂神社に参拝し神通川で鵜飼を賞でるなど国内巡察を行った。この時当地で詠った万葉歌を称え、歌碑に建立し、また平成10年より「売比川鵜飼祭」を再現し家持の業績を偲んでいる。 |

| 鵜坂河 渡る瀬おほみこの吾が馬の |
||||||
| 足掻きの水に衣ぬれにけり |
||||||
| 売比河の 早き瀬ごとに篝さし |
||||||
| 八十伴の男は鵜川立ちけり |
||||||
| 萬葉集巻17 4023 |
|
いかにせむうさかのもりにみえすとも君がしもとの數ならぬ身を これは越の中の國にうさかの明神と申す神の祭の日、榊のしもとして女の男したる數にしたがひて打つなり。女のその折になりて、禰宜に尻をまかせてふせり。禰宜しもとを持ちてをとこの數をとふ。数の如くにはじめのなべの如し。おほかる女は恥がましさにかくして少しをいへば、忽ちにはなぢあえてまさゞまに恥がましき事のあるなり。たゞし、古き歌の見えねばとしよりが歌をしばし書きてさふらふなり。 |

|
越中の国卯坂の神祭の事を思いよりて 卯杖とはうさかの神のきりにけん |
|
うさかの事は書籍に粗見へ侍り。鵜坂寺の縁起ニ曰、白鳳二年五月十五日俄に雷電霰降ル。其夜の中に苗杉ことことく大木トなる。十六日の曉大明神降臨。 |
| 秋なから蠅にあかくや雇ヒ馬 | 句空 |