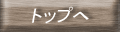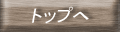2011年〜静 岡〜
清水寺〜碑巡り〜

静岡市葵区音羽町に清水寺という寺がある。

音羽山清水寺

高野山真言宗の寺である。
清水寺本堂

永禄2年(1559年)、今川家臣の朝比奈丹波守元長が建立。開山は京都から迎えられた尊寿院大僧正道因と伝えられている。この地の眺望が京都の音羽山清水寺に似ていたので、その名が付けられた。
清水寺には数多くの句碑がある。
芭蕉の句碑

駿河路やはなたちはなも茶のにほひ
元禄7年(1694年)5月、芭蕉西帰の途次島田宿塚本如舟邸を訪れた際に書き残された句。
明和7年(1770年)5月12日、時雨窓六花庵社中建立。
清水寺の鐘楼

大正8年(1919年)12月、竣工。
登録有形文化財である。
寛永12年(1635年)、梵鐘鋳造。
|
|
昭和18年(1943年)1月、戦争のために供出。
|
|
昭和25年(1950年)、梵鐘復元。
|
小林文母の句碑

はなすりの端山を出たり春の月
『華鳥風月集』(桃路編)に収録されている。
小林文母は大島蓼太の門人。通称庄蔵。
享保8年(1723年)、江戸に生まれる。
天明5年(1785年)、山村月巣の駿府時雨窓を継ぐ。
寛政10年(1798年)11月15日、76歳で没。
観音堂

慶長7年(1602年)、徳川家康建立。
静岡県の有形文化財である。
山村月巣の句碑

名月や心一つの置きどころ
山村月巣は大島蓼太の門人。名は春安。
享保15年(1730年)、出羽寒河江に生まれる。
宝暦14年(1763年)、駿河の時雨窓初代となる。
天明5年(1785年)1月5日、56歳で没。
2011年〜静 岡〜に戻る