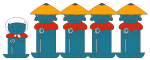下 町〜荒 川〜
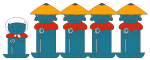
養福寺〜梅翁花樽碑〜
荒川区西日暮里に養福寺という寺がある。

養福寺と文人たち
養福寺は真言宗豊山派の寺院で、補陀落山観音院と号し、湯島円満寺の木食義高(享保3年没)によって中興されたという。
江戸時代、多くの文人たちが江戸の名所である「日暮里(ひぐらしのさと)」を訪れ、その足跡を残した。なかでも養福寺は「梅翁花樽碑」「雪の碑」「月の碑」などからなる『談林派歴代の句碑(区指定文化財)』や、江戸時代の四大詩人の一人、柏木如亭を偲んで建てられた『柏木如亭の碑』、畸人で知られた自堕落先生こと山崎北華が自ら建てた「自堕落先生の墓」などさまざまな文人の碑が残る寺として知られている。
荒川区教育委員会
養福寺仁王門

宝永5年(1708年)、建立。
荒川区指定文化財である。
「自堕落先生の墓」

元文3年(1738年)3月22日、山崎北華は江戸を立ち『奥の細道』の足跡をたどる。松島を訪れ、夢で象潟に遊び、芭蕉に会う。
そゞろ神の。物につきて心を狂はせ。道祖神の招に逢て。取る物手につかず。股曳の破を綴り。笠の緒つけかへて。三里に灸するより。松島の月先心に懸りしと。翁の書き給ひけるぞ誠にて。我にもそゞろ神のつき。道祖神の招き給ふにや。日頃年比。松島心に懸りしに。漸く暇求めて。今年。元文三の年。彌生末の二日。笈背負ひ。草鞋しめて。白河の關越むと志す。今日は殊更日和も麗かなり。
燕に今日往來をば習ひけり
天明元年(1781年)、太田南畝は養福寺を訪れ「自堕落先生の墓」を見ている。
日ぐらしの里に入れば、七面の社あり。衆僧のどきやうの声高し。養福寺といふ寺に、自堕落先生の墓あり。先生は江戸の人なり。五君に鞍がへして志を得ず。髪をからわに結ひ、歯をかねにて染め、佯狂して俳諧師となる。庵を無思庵といひ、軒を不量軒と名づけ、斎を捨楽斎と号し、坊を確蓮坊と称す。昔の反古二卷をあらはす。その中に帰去来の辞を評して、淵明元来金持なるべし、わづかのあれ地をもちて、口をきくこそにくけれと、一口にはり込ししれものなり。
「日ぐらしのにき」
梅翁花樽碑

於我何有哉
|
|
江戸をもつて鑑とす也花に樽
|
|
誹談林初祖 梅翁西山宗因
|
寛政4年(1792年)、二代井原西鶴の百回忌を記念して、谷素外建立。
右側面には西鶴の句が刻まれている。
我恋のまつ島も唯初霞 二祖 松壽軒西鶴
『東都古墳志』(文政2年)に「西山宗因塚」として収録されている。
谷素外は池田氏。大阪の人。建部綾足の門下で、後に江戸に出て談林派七世となる。号は一陽井。
片隅に「梅花佛」の碑があった。

各務支考の供養塔である。
養福寺本堂

戦災で養福寺は仁王門のみを残して焼失した。
昭和40年(1965年)、再建。
下 町〜荒 川〜に戻る