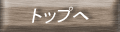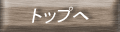2008年〜埼 玉〜
調神社〜かな女の句碑〜

さいたま市浦和区岸町の中山道沿いに調神社がある。

浦和の駅より三町ばかりの此方(こなた)、岸村と云ふにあり。社は街道より右に立たせ給ふ。今、世に月読の宮二十三夜と称せり。別当は月山寺と号して、浦和町の玉蔵院より兼帯す。(新義の真言宗、三宝院の宮に属す。)例祭は九月二十日なり。社の向拝に掲くる調神社の額は、松平信定朝臣の筆跡なり。
祭神 月読命一坐、本地勢至菩薩。(この本地仏により二十三夜の称あり。)
調(つき)神社というのが正しいようだが、地元では「つきのみや」と呼んでいる。
調神社には狛犬の代わりに兎が居る
また、調神社には鳥居が無い。
調神社は延喜式内社。
調神社本殿

由緒 略記
当社は天照大御神、豊宇気姫命、素戔鳴尊の三柱を祭神とする。延喜式内の古社にして、古くより朝廷及び武門の崇敬篤く、調宮縁起によれば、第九代開化天皇乙酉三月所祭奉幣の社として創建され、第十代崇神天皇の勅命により神宮斎主倭姫命が参向、此の清らかな地を選び神宮に献る調物を納める御倉を建てられ、武総野の初穂米調集納蒼運搬所と定めらる。倭姫命の御伝により、御倉より調物斉清の為、当社に搬入する妨げとなる為、鳥居、門を取拂はれたる事が起因となり、現今に到る。
本殿の奥に稲荷社がある。

稲荷社は調神社旧本殿である。
市指定有形文化財(建造物)
調神社旧本殿
調神社は「延喜式」にみられる古社です。この建物は江戸時代中期の享保18年(1733年)に調神社本殿として建立されたものです。型式は一間社流造りです。やねはもとこけら葺きであったと思われます。規模は小さいが木割りは「匠明」という書物に記されているものと一致し、本格的な設計のもとに建立された本殿といえます。また、各所にはめ込まれた彫刻も優れており、特にうさぎの彫刻は調神社と月待信仰の関係を知るうえで貴重です。なを、現社殿が建立された安政年間までこの本殿が調神社本殿として使われていました。
調 神 社
浦和市教育委員会
寛政3年(1791年)4月11日、小林一茶は郷里の柏原に帰る途中で調神社に触れている。
浦和の入口に月よみの宮あり。いさゝかの森なれど、いとよく茂りぬ。
わる眠い気を引立るわか葉哉
享和2年(1802年)4月6日、太田南畝は調神社を通る。
左に若葉の林しげりあひて、林の陰に茶屋の床几などみゆ。月の宮廿三夜堂なりとぞ。
天保2年(1831年)10月11日、渡辺崋山は「毛武」へ旅立ち、浦和宿で調神社のことを書いている。
浦和駅、駅の南に月よみの社社(ママ)あり。額に調神社とかけり。寺を月山寺といふ。
調神社の奥に長谷川かな女自筆の句碑があった。
かな女の句碑

生涯の影ある秋の天地かな
昭和28年(1953年)11月3日、水明松花会建立。
調宮公園句碑
神の留守句碑にあそべる子を咎めず
調宮句碑十五周年千代田にて祝賀
句碑古りぬ椿の実にも馴染み来て
明治20年(1887年)、東京府日本橋区本石町(東京都中央区)に生まれる。
明治42年(1909年)、長谷川零余子(れいよし)と結婚。
昭和3年(1928年)、旧浦和市岸町に移る。
昭和44年(1969年)9月22日、81歳で没。
「それまでの苦難を乗り越え、新天地・浦和を愛し、ここを生涯の地と決めたという、秋の日のしみじみとした気持ちを詠んだ俳句である。」
かな女は、高浜虚子の指導を受け、大正・昭和初期を代表する女性俳人として俳句界の発展に貢獻した。40年余り浦和のこの調神社の近くに居住し、多くの句集・随筆の発刊を通じて、浦和市民並びに埼玉県民の教養の向上と文化活動の普及発展に寄与した。
昭和5年9月に俳誌「水明」を創刊。浦和市名誉市民。埼玉県文化功労賞受賞。紫綬褒章受章。
昭和44年9月22日永眠・享年82歳。同9月27日浦和市葬、勲四等宝冠章受章。
水明俳句会
木瓜(ぼけ)に鵯(ひよどり)

昭和48年(1973年)11月11日、金子兜太は調神社で長谷川かな女の句碑を見ている。
埼玉医師会の俳句会(吟行会)にゆく。仲田邸、広く古く、いい木が多い。そこで会。水明の星野紗一君も一緒。あと、浦和の鰻屋で懇親会。大畑南海魚氏元気。調神社境内、かな女の句碑あり。
『金子兜太戦後俳句日記』
12月12日、調神社で「十二日まち」が開かれる。
浦和宿二・七市場の名残であろう。
平成13年(2001年)、浦和市は大宮市、与野市と合併してさいたま市となった。
2008年〜埼 玉〜に戻る