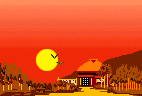良医金氏に案内せられて汐越の橋下より船を入て九十九森八十八潟を漕めくる
|
延享5年(1748年)9月28日、画一庵許虹は新発田を立ち、10月9日に汐越着。象潟遊覧。
明和元年(1764年)9月25日、砂岡雁宕は象潟を訪れている。
明和改元秋九月廿五日到象潟
|
|
| 小鰒よる浪ふところや五湖の秋 | 武凌隠士
| 雁宕
|
明和6年(1769年)5月、蝶羅は嵐亭と共に象潟を訪れ句を詠んでいる。
象潟眺望
|
|
きさがたや波もひとへのうすごろも
| 蝶羅
|
|
象潟や底さへ見ゆる皐月晴
| 嵐亭
|
|
蚶満寺に旅寝して
|
|
さミだれや蚶這かゝる坐禅石
| 蝶羅
|
|
長老の払子さバきや青あらし
| 嵐亭
|
安永2年(1773年)9月4日、加舎白雄は象潟を訪れている。
高波や象潟は虫の藻にすだく
| 東武
| しら尾坊
|
|
安永二年秋九月四日
|
|
象潟やしほ曇れどもゆふ紅葉
| 武陵
| 烏光
|
|
きさかたの岩ね岩ねや秋静
| 勢南
| 斗墨
|
象潟

安永6年(1777年)8月、蓑笠庵梨一は象潟を訪れる。
象潟はうらむに似たりと祖翁の妙詞に、此江の風情は尽たりといふべし。されどたまたま爰に眺望して、其句のなからんは、いと本意なき業なめりと、只空吟、折にふれたるかたちのみを題して
象潟や墨絵の中に花一本
| 梨一
|
天明4年(1784年)9月25日、菅江真澄は小砂川に入って2泊し、27日から29日まで象潟に3泊している。
寛政元年(1789年)8月9日、小林一茶は象潟を訪れた。
一茶27歳の時の句である。
寛政3年(1791年)、吉川五朗は象潟を訪れ、句を詠んでいる。
象潟や森の流るゝ朝かすみ
寛政3年(1791年)5月16日、鶴田卓池は象潟を訪れた。
鳥海山を半めぐりて、けふきさかたにふねをうかぶ。象潟はうらむるが如く、さびしさに悲しさをそへて、といへるけしき、汐ごしに宿をかりて又曙の感に絶(堪)たり。
象潟や浪は新樹の薄萌黄
享和3年(1803年)5月5日、岩間乙二は酒田の常世田長翠を訪ね、象潟に遊ぶ。
文化元年(1804年)6月4日(7月10日)、象潟地震で象潟は隆起し、今は舟を浮かべることは出来ない。
同日、常世田長翠は象潟で大地震に遭い、鶴岡に逃れる。
翌5日、小林一茶は田川で象潟地震を知る。
四日 晴 戌下刻地震
|
|
五日 夜 白雨 六月四日出羽国由利郡地震ニヨリ込
|
当時の通信事情で、そのようなことがありえたのだろうか。
世に名高き跡の。おのづからあれゆくは。あれゆくにつけてなつかし。この象瀉のあらひたるに。荒びたる自然をうしなひしよしは。鳴神の音にのみ聞つたへて。けふしたしく見ることを得たりまことさかしらに。利をさぶるものの一言より。瀉のかぎり田となりて。能因島からす島をはじめ。ありとある島の松も。むなしく早苗吹よのつねの風にかはり果ぬ。さるにても立去がたく。そこらさまよふうち。一村雨の降出て。たゝきさかたのと。ありしむかしのけしきに。かへりたる哀は秋のみにあらず。
明治26年(1893年)8月11日、正岡子規は象潟を訪れた。
十一日鹽越村を經。象潟は昔の姿にあらず。鹽越の松はいかゞしたりけんいたづらに過ぎて善くも究めず。金浦平澤を後にして徒歩に堪へねばしばし路傍の社殿を假りて眠る。覺めて又行くに今は苦しさに息をきらして木陰のみ戀(した)はし。
明治30年(1897年)10月18日、幸田露伴は象潟を訪れている。
桑田碧海の譬喩今さら驚かんは愚なる事ながら、流石眼のあたりに之を見ては又もや今我が立てるあたりの渦巻く淵と成らんも知れずと、そゞろにえりもと寒き思ひす。蚶満寺といふを訪へば小き沙彌出で来りて、これは西行桜なり、これは時頼躑躅花なりなんどと片腹痛きことを云ふのみならず、神功皇后此地より船出したまひしを以て山号を皇后山といひ、纜(ともづな)を解きたまひたるところを唐が崎といふなどと語り出づ。進藤和泉といへる者の著せる出羽国風土略記巻の八にも此事見えたれば、沙彌はたゞ虚談を伝ふるのみにして罪無けれども、その始め有らぬことを云ひ出したるもののさかしら悪むべし。
「遊行雑記」
明治35年(1902年)、三森幹雄は象潟で句を詠んでいる。
見れば見るほど象潟の夏寒し
明治36年(1903年)8月、田山花袋は象潟を訪れ、「羽後の海岸」を書いている。
蚶満寺の山門の松樹の間に陰見せるを認めて直ちに車を下りてこれを訪ふ。蕭然たる村寺にして、本堂の徒に広大なる、茅葺屋根の半傾きかけんとしたる、また旧跡を弔ふにかなへり。雛僧客の到れるを聞きて、則ち導を為してこれを説く。曰く、かの大なるは弁天島、此方に見ゆるは猿島、磯鳩、昔は海水一面にこの地を浸して、その風景は奥の松島にも勝りたりしをと。あゝその口吻また何ぞ無限の感を籠めたるや。
西行船繋の桜、芭蕉翁自筆の碑を見て、本堂に帰れば、寺僧今年は恰も象潟震災の百年に当りたりとて、紀念の為めに製したる絵端書を売る。現今の象潟の風景を写真版にしたるのみにて、其絵甚だ興なけれど、都の友に頒たばやと七八葉を買ひて去る。
『草枕』(明治36年、隆文館刊)所収
明治40年(1907年)8月4日、河東碧梧桐は象潟を訪れた。
道にマイ瑰(カイ)の実の真赤になったのを摘んで、試にこれを口にしながら象潟に着いたのは日もすでに海に落ちて、暮色蒼然たる時であった。干満珠寺の山門をくぐった十歩ばかりに、撞きそめた鐘の音がゴーンと物静かな中に響く。なお近づくにつれて、鐘の余音が耳に澄み渡る木も石も見わかぬ寂然たる暗中に、詩興の湧くような思いをしておると、壷庭(こてい)の案内をするという僧の声がこの詩興を掃うて、我等を寺の庭に導いた。
「マイ瑰」はハマナスのこと。
昭和2年(1927年)10月、小杉未醒は「奥の細道」を歩いて、象潟を回顧している。
日本海の潮がせまい水口、汐越しと稱する處から出入する、底淺き入江、ぐるりと廻つて三里足らず、九十九の島あり、八十八の浦曲あり、島ごとに松生へ、松の下にねぶの木多く、夏となれば、かそけき紅白の花を着ける、其の島々の松と合歡の木は今もあるが、文化年間鳥海山噴火の餘勢で、地盤の隆起の爲に、入江の水は日本海へ放下されて、底の藻草も乾き、小魚共も途方に暮れたであらう、
大正11年(1922年)3月31日、竹久夢二は象潟を訪れた。
大正14年(1925年)8月23日、荻原井泉水は象潟を訪れ、蚶満寺で芭蕉の真蹟を見ている。
私達は、この寺に伝える芭蕉の真蹟を見せてもらうために、庫裡に案内を乞うた。幸に方丈に通してくれた。その方丈である、芭蕉が書いているのは――
『随筆芭蕉』(象潟のまぼろし)
昭和18年(1943年)8月2日、小杉放庵は象潟を訪れた。
昭和22年(1947年)10月22日、斎藤茂吉は象潟を訪れ、歌を詠んでいる。
象潟の蚶滿禪寺も一たびは燃えぬと聞きてものをこそ思へ
あかあかと鳥海山の火を吹きし享和元年われはおもほゆ
『白き山』
巌谷小波の句もある。