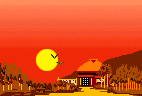『奥の細道』 〜東北〜
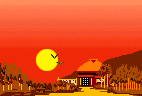
〜「おくのほそ道」の碑〜
仙台市宮城野区岩切の七北田川沿いに東光寺という寺がある。

東光寺の石段

元禄2年(1689年)5月8日(新暦6月24日)、芭蕉は仙台を立ち、十符の菅・壺碑を見ている。
一 八日
朝之内小雨ス。巳ノ尅ヨリ晴ル。仙台ヲ立。十符菅・壺碑ヲ見ル。
『曽良随行日記』
十符の菅(とふのすげ)は編み目が10筋ある菰を編むための菅(すげ)。
おくの細道は、名所に非ず。十符の里は、名所也。新古今、見し人もとふの浦かぜ音せぬにつれなく消る秋の夜の月、橘為仲。
金葉、水鳥のつらゝの枕ひまもなしむべさへけらし十符のすがごも、経信。方角抄、みちのくのとふの萱菰七ふには君を寐させてみふに我ねん。
『奥細道菅菰抄』
石段の右手に「おくのほそ道」の碑があった。

かの画図にまかせてたどり行けば、奥の細道の山際に、十符の菅あり。
「おくのほそ道」の本文に、題名となった奥の細道の記述がある。この付近から東へ続く古道に由来している。
平成元年(1989年)11月23日
元禄9年(1696年)、天野桃隣は「十符の菅」のことを書いている。
仙台より今市村へかゝり、冠川土橋を渡り、東光寺の脇を三丁行テ、岩切新田と云村、百姓の裏に、十符の菅アリ。又同所道端の田の脇にもあり。両所ながら垣結廻らし、菅は彼百姓が守となん。
元文3年(1738年)4月、山崎北華は『奥の細道』の足跡をたどり、奥の細道、十符の井を訪ねている。
是より奥の細道。十符の井を尋ねて。沖の井に行く。三間四方程の岩なり。周は池なり。里人は沖の石といふ。千曳(ちびき)の石も此あたりと雖も。里人は知らず。末の松山は此所より遙に海原に見ゆ。
元文3年(1738年)4月、田中千梅は十符の菅を訪ねている。
原の町今市と云里を行けは奥乃細道所之者ハ吾妻海道ト云古道也山陰に轟の橋を渡り十符の菅を尋ねて山際を左に草むらの中を分入離れ家の後ロに昔の跡失ハす菅沼ありて験(シルシ)をたつ今も國乃守へ菅薦を編て捧ルとなん
寛延4年(1751年)、和知風光は『宗祇戻』の旅で「十符の菅」で句を詠んでいる。
十府の菅 此辺志波彦の神社有旧跡也
時雨なは十府の菅蓑ほしからめ
宝暦2年(1752年)、白井鳥酔は「十符の菅」のことを書いている。
○十符の菅
岩切村冠川あたり近きに百姓佐左衛門といへるものゝ後に十尺はかり四方の菅田あり名のみ未枯て寂し我三符に寐んとよめるむかしを聞は
今は鴫の寐るにもせまし十符の菅
明和6年(1769年)4月、蝶羅は嘉定庵の社中に「十符の菅」へ案内された。
十苻菅
|
|
三苻に寝た情のはしや菅の守リ
| 蝶羅
|
|
我笠を見てさへ嬉し十苻の菅
| 野月
|
|
民草をまねけバ凉し十苻の菅
| 東明
|
明和7年(1770年)、加藤暁台は奥羽行脚の旅で「十符の菅」を訪ねている。
長柄の橋屑、井手の蛙懐にせし例しも有ながら夫を摘。是をとりてつとに得させよといへる老法師が事おもひ出て、一もと刈とり笠にはさむ。七布の誠もあるものを。