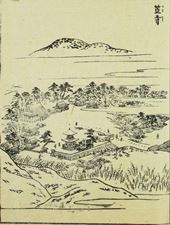芭蕉の句碑

星崎の闇を見よとや啼千鳥
名古屋市南区笠寺町上新町の旧東海道沿いに笠覆寺という寺がある。

笠覆寺山門

真言宗智山派の寺である。
天林山と号し、真言宗。
俗に笠寺観音の名で知られ、尾張四観音の一つである。
天平年中(729〜)禅光上人の開基で、十一面観世音を安置する。
初め小松寺と称したが、延長年中(923〜)藤原兼平が堂宇を再興し、今の寺号に改めた。のち再び荒廃したが、嘉禎4年(1238年)僧阿願が朝廷に願い出て、宜陽門院庁より田畑の寄進を受け堂塔を建立した。当寺には重要文化財・県指定文化財多数がある。
天林山笠覆寺

笠寺観音と玉照姫の歴史
・開基
呼続(よびつぎ)の浜辺に流れ着いた霊木が夜な夜な不思議な光を放ち、人々はそれを見て恐れをなした。
近くに住んでいた僧・善光上人は夢のお告げを受け、その霊木を彫って十一面観世音菩薩の像を作った。
上人は寺を建て、そこに観音様をおさめ、その寺を「天林山小松寺」と名付けた。
・玉照姫と観音様
その後、約200年の歳月が流れ、小松寺は荒廃、お堂は崩壊し、観音様は風雨にさらされようになっていた。
ここに一人の美しい娘がいた。彼女は鳴海長者・太郎成高の家に仕えており、その器量を嫉まれてか、雨の日も風の日も、ひどくこき使われる日々を送っていた。
ある雨の日、ずぶ濡れになっていた観音様をの姿を見た彼女は、気の毒に感じ、自分がかぶっていた笠をはずして、その観音様にかぶせたのであった。
その縁か後日、関白・藤原基経公の息子、中将・藤原兼平公が下向のおり、長者の家に泊まった際にその娘をみそめ、自分の妻として迎えようと決心した。
兼平公の妻となった娘は、それから「玉照姫」と呼ばれることとなった。
この観音様の縁によって結ばれた玉照姫・兼平公夫妻は、延長8年(930年)、この地に大いなる寺を建て、姫が笠をかぶせた観音様を安置した。このとき寺号も小松寺から「笠覆寺」に改めた。
多宝塔

芭蕉は笠寺の縁起を聞いて、句を奉納している。
この御寺の縁記(起)、人の
かたるを聞侍て
かさ寺やもらぬ岩屋もはるのあめ
武城江東散人芭蕉桃青
笠寺の発句度々被二仰下一候故、此度進覧申候。よきやうに清書被レ成、奉納可レ被レ成候。委曲夏中可レ得二御意一候。 以上
寂照叟
貞亨4年(1687年)春と思われる書簡である。
寂照は下里知足の法名。
尾張の国笠寺を通りける時、宝前
|
にてこの句を見付侍るよし、ある
|
人かたりけれは
|
|
笠寺やもらぬ岩屋も花の雨
| 翁
|
『芭蕉句選拾遺』に「笠寺や窟(いわや)ももらす五月雨」とある。
此句、尾陽笠寺の絵馬に哥仙有。貞亨五辰五月吉日と記ス。浅井氏是を写ス。
元禄5年(1692年)5月16日、貝原益軒は笠寺に至る。
十六日。雨ふる。万場、岩塚を過、熱田にいで鳴海にゆく。右の方の海辺に宵月の浜あり。空はれし時は、海人の家、塩屋など見ゆれど、けふは曇りて見えず。星崎、夜寒の里など云名所、皆其あたりに近し。笠寺に至る。此寺、号は竜福(ママ)寺天林山と号す。此寺、道の側にあり。
元禄16年(1703年)10月、岩田涼菟は笠寺で句を詠んでいる。
多宝塔の左奥に「春雨塚」があった。

此御寺の縁起人の
|
かたるを聞侍りて
|
| 芭蕉翁
|
笠寺やもらぬ岩屋も春の雨
| 桃青
|
|
旅寢を起す花の鐘撞
| 知足
|
|
かさ寺や夕日こほるゝ晴しくれ
| 素堂
|
|
大悲のこのは鰭となる池
| 蝶羽
|
蝶羽は知足の子風和。千代倉家三世。素堂の門人。
正徳2年(1712年)10月9日、素堂は蝶羽と共に笠寺へ。
十月九日 晴天 素翁逗留。昼より松風、寝覚、呼続、笠寺、上野一見ニ同道スル。
塩焼日最一度見たし霜煙
| 素堂
|
浦風や塩焼ぬ日も霜煙
| てうウ
|
浦の浜いつもあけぼの雪の雪の塩
| キ世
|
笠寺や夕日こぼるゝ雪の塩
| 素堂
|
笠寺や凩着する木の葉蓑
| てうウ
|
笠寺やもらぬ岩屋も春の雨
草の庵なに露けしとおもひけん漏らぬ岩屋も袖はぬれけり。笙の窟にて、僧正行尊。
碑陰に「亀世」の句が刻まれている。
かさ寺や浮世の雨を峰の月
亀世は知足の四男鉄叟。千代倉家四世。素堂の門人。
亀世の子が下郷学海。
明和元年(1764年)、77歳で没。
安永2年(1773年)10月、春麗園蝶羅建立。野菊庵秋色書。
蝶羅は蝶羽の子。蓼太の門人。
安永5年(1776年)、54歳で没。
秋色は三世湖十の門人。
天明4年(1784年)5月20日、58歳で没。
明治44年(1911年)5月26日、河東碧梧桐は笠寺に寄り道して芭蕉の句碑を見ている。
五月二十六日。晴。
熱田神社に詣で、笠寺に道寄りして、芭蕉の「笠寺や漏らぬ窟(ママ)春の雨」の句碑を見た。漏らぬ窟というのは、本尊十一面観世音の笠召したるが、頬まで隠れておるのに思い寄せた事であろうか、など寺内を巡覧しつつ、芭蕉の「ねさめは松風の里 呼続は夜明てから 笠寺は雪の降る日」という詞を想い出した。
本堂の右手に「千鳥塚」があった。

星崎の闇を見よとや啼千鳥
出典は『俳諧千鳥掛』。
貞亨4年(1687年)11月7日、寺島安信宅で巻かれた歌仙の発句。
歌仙が満尾した記念に千鳥塚を建立している。
碑陰及び両側面
寝覚めは松風の里 呼つぎは夜明けてから 笠寺は雪の降る日
芭蕉翁ハ東西南北ノ人也、此処ニ之キ此処ニ駐リ吟哦ヲ絶タズ昔年尾張ノ星崎ノ濱ニ遊ビ一句ヲ留メテ去ル、其ノ遺墨余カ家ニ藏ス、今ヤ之ヲ斯ノ地ニ収メ土ヲ築キ碑ヲ建テ、後人ヲシテ翁ガ清遊吟嘯ノ地ヲ知ラシメント欲スト爾カ云、銘ニ曰ク、翁ヤ僊カ八紘ニ逍遙スト。 享保己酉冬 丹以之 恭建
享保14年(1729年)冬、丹羽以之建立。
最古の芭蕉句碑といわれる。2番目は「水鶏塚」。
以之は名古屋の医者。通称は浅野屋治右衛門。支考の門人。千鳥庵。
『諸国翁墳記』に「千鳥塚 尾州笠寺境内ニ在 名古屋 以之建」とある。
山口誓子は、笠寺を訪ねて2つの句碑を見ている。
新しい感じの御影石が崖の縁に立っていた。下は墓地で、その向こうは丘である。木立はなくなっている。僅かに墓地の右手に、高畠達四郎の描いたような木が一本立っている。
この句は「芳野紀行」に出て、「鳴海にとまりて」という前書がついている。知足の家に泊ったときの句だ。
昔は、笠寺から南をすべて星崎と云ったが、そこは千鳥の名所だ。闇の中で千鳥が鳴く。その声は星崎の闇をよく見よ、闇に眼を凝らせという誘いかけの声だ、というのだ。
享保十四年の建立。知足亭に残っていた芭蕉の真蹟に拠ったということである。書には文句の附けようがない。
「東海道名所図会」巻三に笠寺の挿絵が載っている。よく見ると、前方の「笠寺や」の碑も、後方の「星崎の」の碑も描かれている。この名所図会をよく見て来ればまごつかなかったのに。
笠寺
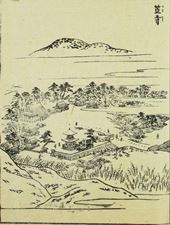
「東海道名所図会」巻三
「笠寺」は『東海道中膝栗毛』にも出ている。
田ばた橋をうちわたり、かさでら觀音堂にいたる。笠をいたゞきたもふ木像なるゆへ、この名ありとかや
執着のなみだの雨に濡れじとやかさをめしたるくはんをんの像
西門に「暁台塚」があった。

さむ空にたゞ暁の峰の松
風化して、ほとんど読めない。
享和3年(1803年)春、士朗建立。
徳川家康は6歳の時に人質として駿府へ送られる途中、戸田康光の裏切りにより尾張国の織田信秀(信長の父)の那古野に送られた。2年後、前年安祥城の戦いで生け捕りにされてた織田信長の異母兄信宏と笠寺観音境内で人質交換された。
人質交換之地

宮本武蔵の碑があった。

笠寺一里塚へ。
芭蕉の句碑に戻る