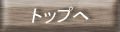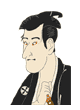
海軍操練所跡
幕末・維新ゆかりの地
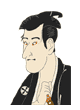
海軍操練所跡

|
万延元年(1860年)1月、幕府は遣米修好使節団を公式に派遣した。その際、勝海舟は、咸臨丸(300トン)の艦長として、万里の波浪と戦いながら一行の護衛と海洋技術習得の大任を果たしたのである。これ、日本人による最初の太平洋横断であり、わが航海史上、特筆大書すべき壮挙であった。 文久3年(1863年)4月、攘夷の世論ようやく急を告げ、徳川家茂は摂海防備のため阪神海岸を巡視した。当時、海舟は、軍艦奉行並の職にあって、これに随行し、神戸港が天然の良湊であり、国防の要港であることを力説した。かくて、ここ小野浜の地に海軍操練所の創設をみたのである。 この神戸海軍操練所は、兵学校、機関学校、海軍工廠を総合した観があり、大規模な組織であった。勝海舟はここに天下の人材を集め、日本海軍の礎を築き、海外発展の基地をつくろうとした。その髙風を仰ぎ、来り学ぶ俊英200の多きを数え、坂本龍馬、陸奥宗光、伊東祐亨など、幾多有為の人材が輩出したのである。 元治元年(1864年)、海舟は、禁門の変に操練生の一部が反幕軍として参加したため、激徒養成の嫌疑を被って解職され、操練所もまた翌慶応元年(1865年)3月、ついに閉鎖されるの止むなきに至ったのである。 当時は、この「記念の錨」から東へ長くひろがり、南は京橋詰から税関本庁舎を望むあたりの、長方形の入堀約1万坪の一帯が海軍操練所であった。惜しくも現在では阪神髙速道路の下に埋め立てられて、当時の盛観をしのぶに由もない。今はただ、遠く諏訪山公園からこの地を見守る勝海舟直筆の碑文を仰ぐことのできるのがせめてもの救いである。 ここに当時を偲び郷土を愛する人びとに、この記念の碑を捧げる。 |