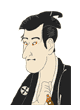下 町〜荒川区〜
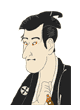
熊野神社〜源義家ゆかりの地
百観音円通寺から国道4号(日光街道)を行く。
千住大橋の手前で路地を入ると、熊野神社があった。

熊野神社

小さな社殿と大きな石燈籠があった。
熊野神社
創建は永承5年(1050年)、源義家の勧請によると伝えられる。
大橋を荒川(現隅田川)にかける時、奉行伊奈備前守は当社に成就を祈願し、文禄3年(1594年)橋の完成にあたり、その残材で社殿の修理を行った。以後、大橋のかけかえごとの祈願と社殿修理が慣例となった。
また、このあたりは材木、雑穀などの問屋が建ち並んで川岸(かし)とよばれ、陸路奥州道中と交差して川越夜舟が行きかい、秩父・川越からの物資の集散地として賑わった。
荒川区教育委員会
源義家は鎮守府将軍頼義の長男で、義朝の祖父、頼朝の曾祖父。
同北の方千住川の端にあり。祭神伊弉冊尊一坐。社殿に云く。永承年中義家朝臣奥州征伐の時、此地(ここ)に至り河を渡らんとするに、奇異の霊瑞あり。故に鎧櫃に安ぜし紀州熊野権現の神幣(みてぐら)を、この地にとゞめて熊野権現と斎きたてまつるといへり。
按ずるに、熊野権現・飛鳥明神、何れも紀州に鎮坐あり。又この地に両社あるも、所謂(いはれ)あるべきことなれども、今伝記とりどりにして詳なることを得ず。余説を設けんと欲(す)るといへども、しげきをいとひてこゝに略す。
下 町〜荒川区〜に戻る