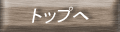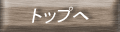2008年〜埼 玉〜
安養院〜小倉家の墓碑群〜

埼玉県本庄市に安養院という寺がある。

安養院

安養院
安養院は曹洞宗の寺で、山号を若泉山、寺号を無量寺という。本尊は無量寿如来で、ほかに脇立として観音と勢姿の二菩薩がある。
寺伝によると、創立は文明7年(1475年)という。武蔵七党の一党である児玉党の一族本庄信明の弟藤太郎雪茂が仏門に帰依して、当時の富田村に安入庵を営んだが、水不足に悩まされたため、安養院を開基したと伝えられる。以後、付近は水不足に悩まされることもなく、周辺の人々から“若泉の荘”と呼ばれるようになったという。
埼 玉 県
本 庄 市
寛政4年(1792年)10月5日、栗庵似鳩は信濃に旅立ち、安養院に詣でた。
是より道急きて本庄駅に出て、武政一馬子か瓢庵に雨具取て一泊、風談の暇あれは、傘・木履なんとかりて○安養院に詣、釣牛禅師の快く主饗ありて興して帰る。道すから帯屋或は望田李明なとを尋て夕方瓢庵に帰て、夜更る迄風談す。此霄釣牛和尚使僧をもて、こんふ、白かねなとに文添て餞別せらる。末に
略詞書
|
|
ちる楓紅葉といふて別れけり
| | 釣牛
|
|
雪の度心をあれや京参り
| | ゝ
|
|
見送りの跡や庵の時雨月
| | ゝ
|
釣牛和尚は安養院住職。
可都里『名録帖』に「釣牛同 安養院」とある。
安養院本堂

安養院に「小倉家の墓碑群」があり、本庄市指定文化財になっている。
「小倉家の墓碑群」に芭蕉の句碑があるというので、探してみた。
「小倉家の墓碑群」は長い間風雨にさらされて、よく分からない。
どうやらそれらしいものを見つけた。
芭蕉翁碑

言ば唇寒し秋の風
謝蕪村の筆意にならひ 隆古
小倉紅於建立。
本庄宿の旅籠「小倉屋」の主人。久米逸淵門の俳人。
紅於は邸宅「小倉山房」に本庄宿を往来する文人墨客を招いていた。
「三俳人句碑」があった。

酒買に行くや雨夜の雁一ツ
| 其角
|
ふとんきて寝たる姿やひがし山
| 嵐雪
|
はつれはつれ粟にも似たる薄かな
| その女
|
「崋山戯墨」とある。
渡辺崋山も度々「小倉山房」を訪れていたようだ。
明治16年(1883年)3月28日、70歳で没。
紅於の句
安養院には戸谷双烏の墓もある。
2008年〜埼 玉〜に戻る