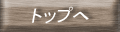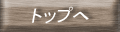2004年〜長 野〜
海野宿〜白鳥神社〜


新鹿沢温泉から県道94号東部嬬恋線を下り、左折して国道144号に入る。

鳥居峠を越えると、長野県。
左折して、県道4号真田東部線に入る。

カーナビの指示に従って右折し、海野宿へ。

海野宿

駐車場に車を停める。
使用料は300円(東部町海野宿駐車場条例:平成15年4月1日施行)。
白鳥神社があった。

白鳥神社
この神社は古代天皇の命を奉じて東征の途についた日本武尊(やまとたけるのみこと)がこの地に滞在されたことから白鳥神社と稱し、古代から中世の豪族、海野氏の祖と云われる貞元親王・善淵王・海野広道公を祭神としています。
白鳥神社の南を流れる千曲川の白鳥河原は木曽義仲挙兵の地だそうだ。
木曽義仲挙兵の地(海野郷白鳥河原)
治承5年(1181年)義仲27歳の6月、後白河法皇の第二皇子高倉宮以仁王(もちひとおう)の令旨(りょうじ)に応じ、平家追討のため大豪族海野氏の根拠地であるここ海野郷「白鳥河原」に挙兵した。
馳せ参ずる者、地元滋野一族をはじめ、義仲の四天王樋口次郎兼光・今井四郎兼平・根井小弥太・楯六郎親忠の武将を中心に、信濃、西上州の将兵等約3千余騎が集結した。
白鳥河原で挙兵した義仲は、まず平家の先鋒越後国の城氏の大軍約6万余騎を横田河原にて撃破し、つづいて寿永2年(1183年)5月、越中と加賀の国境砺波山の戦で平家の大群を破り、北陸道・近江を制圧し、同年7月京都入りをはたした。
翌年の寿永3年(1184年)1月、征夷大将軍に任ぜられたが、その十数日後、宇治瀬田の戦で敗れ、近江粟津で戦死した。
東部町教育委員会
白鳥神社の隣に「日本の道100選」の碑があった。

海野宿の町並み

旅篭屋造りの「海野宿資料館」。
2階は「出桁造り」で、海野格子がある。奥には本卯建が見える。
「海野宿資料館」の脇に一茶の句碑がある。

夕過の臼の谺の寒哉 一茶
文化9年11月海野宿泊
小林一茶は15歳で江戸に出る。
文化9年(1812年)11月14日、一茶50歳の時、江戸を引き上げる。22日、海野宿に泊まる。
廿二晴 海野泊
夕過の臼の谺の寒哉
『七番日記』(文化9年11月)
24日、柏原に帰る。
町並みの柳

海野に加舎白雄の門人齋藤雨石・井々がいた。
2004年〜長 野〜に戻る