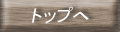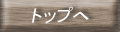私の旅日記〜2009年〜
榴岡天満宮〜碑巡り〜

仙台市宮城野区榴ヶ岡に榴岡天満宮(HP)がある。

文明19年(1487年)、道興准后は榴ヶ岡を越えて歌を詠んでいる。
つゝじが岡を越え行きけるに、わらびをみて、
名にしおふ躑躅か岡の下蕨ともに折りしる春の暮れかな
寛文7年(1667年)7月25日、天満宮は現在の東照宮の地より御遷座。
榴岡天満宮

躑躅岡
|
|
とりつなげ玉田横野のはなれ駒
|
つゝじが岡にあせみ花咲
|
此歌は、河内国の玉田横野の題にあり。此処にも玉田横野と云処ありといへり、さだかにしれず。又鞭舘とて錦戸太郎国衡出張(でばり)城の跡也。今天神の社あり、無双の景地也。予独吟奉納十日万句の巻頭に
、
御月ありかゝげ奉る一万灯
| みち風
|
|
又のとし、大矢数満座のよろこびの会に、
|
<ミチバ>
|
とんたり梅三千羽のそやをゑ(え)たりやあふ(う)
| 同
|
境内には芭蕉の句碑や大淀三千風追善碑などが多数建ち並んでいる。
大淀三千風追善「萬句俳諧奉納記」碑

享保8年(1723年)、建立。
境内にある碑の中で最も古いもの。
大淀三千風は寛永16年(1639年)に伊勢射和の商家に生まれる。31歳の時から45歳まで15年間仙台に住んだ。
天和3年(1683年)5月4日、仙台を立って『日本行脚文集』の旅に出る。
貞享3年(1686年)10月から翌4年3月まで仙台の亀岡八幡宮に滞在している。
元禄2年(1689年)5月5日(新暦6月21日)、芭蕉は三千風を訪ねたが、三千風は既に仙台を離れ、『日本行脚文集』の旅にあった。
5月7日、芭蕉は榴岡天満宮を訪れている。
榴岡天満宮拝殿

元禄9年(1696年)、天野桃隣は『奥の細道』の跡をたどり、榴岡天満宮に触れている。
山榴岡・釈迦堂・天神宮・木の下薬師堂。宮城野、玉田横野 何も城下ヨリ一里ニ近し。
社務所の前に芭蕉の句碑があった。

花咲て七日鶴見る麓かな
出典は『俳諧一橋』(清風編)。
貞亨3年(1686年)3月20日、鈴木清風の江戸の屋敷で開かれた歌仙の発句。
明治29年(1896年)4月、建之。
地元の俳人6人の句が刻まれている。
寛保元年(1741年)、雲裡房は仙台に住む。山本白英の尽力で冬至庵を結ぶ。
芭蕉の句碑がもう1基ある。

あかあかと日はつれなくも秋の風
元禄2年(1689年)7月、『奥の細道』の旅で金沢から小松へ向かう途中に詠まれた句。
寛保3年(1743年)2月7日、芭蕉五十回忌、支考十三回忌追善で雲裡房が建立。
『諸国翁墳記』に「月日塚 奥州仙臺躑躅岡ニ在 冬至菴連中建」とある。
仙台市の指定登録文化財である。
芭蕉の句と並んで、各務支考の句が刻まれている。
十三夜の月見やそらにかへり花
寛延4年(1751年)、和知風光は『宗祇戻』の旅で榴ヶ岡を訪れた。
躑躅岡 桜ひしと有にて
此岡につゝしの替り枯さくら
雲裡房の句碑もあった。

羨めど崩れて見せる牡丹かな
宝暦13年(1763年)、冬至庵止鳥庵連中建之。
雪中庵蓼太の句碑

五月雨やある夜ひそかに松の月
松は「待つ」の掛詞。
寛保2年(1742年)4月13日、雪中庵蓼太は奥の細道行脚に出る。10月6日、江戸に戻る。
嚢菴白麻建之。
明和7年(1770年)、加藤暁台は奥羽行脚の旅で榴ヶ岡を訪れている。
曰人の句碑

道ばかり歩いてもどる枯野かな
遠藤曰人は仙台藩士。名は定矩、字は文規、通称清左衛門。
天保7年(1836年)歿、77才。

暮るともみちは苦はなし月と花
| 梅月庵喜鳥
|
|
いますこしすこしとぬれつ花の雨
| 惟草庵寥岱
|
惟草庵寥岱は江戸神田の人。巒寥松の門人。
天保14年(1843年)3月、建立。
嘉永6年(1853年)1月6日、寥岱没。
その他、仙台の俳人の句碑も数多くある。

寂しさは生れつきなり松の花
| 百非
|
|
木の葉火のぺらぺら過る月日かな
| 巣居
|
|
ふるるものみな輝きぬけふの月
| 心阿
|
巣居は原町の観音堂別当。白居の門人。
百非と心阿は巣居の子。
嘉永4年(1851年)8月、蘭庭夢庵社中建立。

梅ちりてはてなき水の月夜かな
| 松洞馬年
|
馬年は石原泰輔。仙台藩士。
嘉永4年(1851年)5月25日、宗古建立。菊庵書。

我こころわれにもとらず花の中
| 松洞宗古
|
|
わかれても心は花にとまりけり
| 月下庵梅雲
|
宗古は馬年の門人。二世松洞。
宗古の子亀子の句碑が瑞巌寺にある。

世に競べ身にくらべけり竹の露
| 禾月
|
禾月は仙台藩士横田始成の息女。乙二の門人。

細くとも流れぬはなし春の水
| 舎用
|
舎用は小島一章。五梅庵。曰人の門人。
瑞巌寺の「芭蕉翁奧の細道松島の文」の碑に曰人、禾月、宗古、心阿、舎用の句が刻まれている。
嘉永5年(1852年)3月19日、吉田松陰は榴岡天満宮のことを書いている。
街市の東邊躑躅丘に至る、一に釋迦堂と名づく。地稍高敞にして平田に臨み、天神の祠を建つ。
明治26年(1893年)7月29日、子規は榴ヶ岡に遊んだ。
二十九日つゝじが岡に遊ぶ。躑躅岡とも書き石榴岡とも書きて古歌の名所なり。仙臺停車場のうしろの方にあたれり。杜鵑花は一株も見えざれど櫻樹茂りあひて空を蔽ひ日を遮ぎり只涼風の腋下に生ずるを覺ゆ。
私の旅日記〜2009年〜に戻る