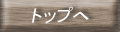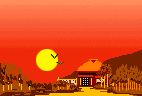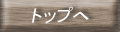私の旅日記〜2015年〜
松島遊覧船〜鐘島〜
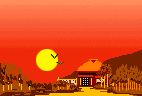
嘉永5年(1852年)3月17日、吉田松陰は松島から舟で塩竈へ。
又一小坂を越えて松島に至り、舟にて鹽竈に至る。二里半なり。陸行すれば則ち三里と云ふ。是の日、陸行七里半。夜雨。
松島には何度も来ているが、遊覧船に乗ったことがない。
今日は遊覧船に乗ってみることにする。

松島遊覧船「仁王丸」

料金は1,500円。
割引チケットがあるのを知らなかった。
鐘島

4つの横穴があいている。
外洋に出ると、波が荒い。
仁王島

後ろは桂島であろう。
第二「芭蕉丸」

そんなにいい写真は撮れないものだ。
明治26年(1893年)7月29日、正岡子規は塩竈から小舟で松島を漕ぎ出す。
小舟をやとふて鹽竈の浦を發し松島の眞中へと漕ぎ出づ、入海大方干潟になりて鳬(かも)の白う處々に下り立ちたる山の緑に副へてたゞならず。先づ第一に見ゆる小さき島こそ籬が島にはありけれ。此の島別にさせる事もなきも其の名の聞えたるは鹽竈に近き故なるべし。波の花もて結へると詠みたるも面白し。
涼しさのこゝを扇のかなめかな
(中 略)
船頭のいふ、松島七十餘島といひならはせども西は鹽竈より東は金華山に至る海上十八里を合せ算ふれば八百八島ありとぞ傳ふなる。見給へやかなたに頂き高く顯はれたるは金華山なり。こなたに聳えたる山巓は富山觀音なり。舳に當りたるは觀月樓、樓の右にあるは五大堂、樓の後に見ゆる杉の林は瑞岩寺なり。瑞岩寺の左に高き建築は觀瀾亭、稍々觀瀾亭に續きたるが如きは雄島なり。いざ船の着きたるにたうたう上り給へといふ。恍惚として觀月樓に上る。
涼しさの眼にちらつくや千松島
私の旅日記〜2015年〜に戻る