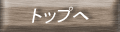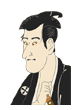

尾山神社〜「利家とまつ」〜

|
初代加賀藩主前田利家公と正室おまつの方を御祭神とする当神社は、明治6年(1873年)に歴代藩主の別邸であった金谷御殿跡に建立された。 ギヤマンがはめ込まれたり、和・漢・洋折衷様式を見せる神門は、異国情緒漂う造り。東神門は金沢城で唯一残る桃山風御殿様式の門で、旧金沢城二の丸にあった唐門を移築したものである。 旧金谷御殿の庭であり、築山地泉回遊式の庭園は、江戸末期に作庭されたもので、かつて辰巳用水を 引き入れた池には、三つの島と趣向 を凝らした橋が配され、書院庭園の面影を色濃く残している。 |




|
平成12年(2000年)10月、平成14年度NHK大河ドラマ「利家とまつ」の放映を記念して建立。原作者は米林勝二・山瀬晋吾・湊真佐夫。 |
|
昭和60年(1985年)10月22日、白鳥路に室生犀星像設置。米林勝二作。 昭和60年(1985年)10月22日、白鳥路に徳田秋聲像設置。山瀬晋吾作。 |
|
流れ矢を防ぐために、鎧の背にかけた布のことを言います。 その後時代の推移により、風にふくらんだ形を示すために、竹串、鯨の骨類、ひげ等を骨組みに入れるようになり、これを母衣と呼びました。 戦国時代(西暦1560年頃)に騎馬武者は、これを背に戦場を駆け巡り、連絡の役をつとめました。このような騎馬武者を母衣衆と呼びました。 織田軍団の母衣衆は、佐々成政を筆頭とした10人の黒母衣衆と、前田利家を筆頭に9人の赤母衣衆とで合計19人でした。 そして、戦闘となれば、諸隊のガイド的役割もあり、敵にとって目に付きやすく、大変危険でもありました。 |

|
名は「まつ」といい、前田利家の正室で、天文16年(1547年)7月9日尾張の国に生まれる。12才の時に9才年上の前田利家に嫁ぎ2男9女を儲ける。賤ヶ岳の戦いには 、柴田勝家に味方して敗れた前田利家に代って豊臣秀吉との和議に尽力された。お松の方は利家と戦国乱世を共にし、加賀藩を外柔内剛にて支えられました。利家没後は芳春院と号す。慶長5年(1600年)徳川家康が、前田家に嫌疑をかけた際、人質として江戸にて15年間忍従に耐えぬき、慶長19年(1614年)金沢に戻った。元和3年(1617年)金沢城にて71歳の生涯を終える。正に戦国烈女の鑑であり、加賀百万石の母と敬われる。 平成14年NHK大河ドラマ「利家とまつ 加賀百万石物語」放映決定を記念し、前田家当主、尾山神社のご理解をいただき、若き日のお松の方の座像を境内のこの地に建立した。 |


| 報恩感謝は人類最高の道義であり、この教えの顕現を念じ、報恩の象徴として、母子順風之像を建立する。 |

|
昭和56年(1981年)、倉敷駅南口に「鶴の親子順風の像」設置。 平成元年(1989年)6月22日、平野富山は78歳で死去。 |


|
明治40年(1907年)、兵庫県氷上郡芦田村(現:兵庫県丹波市青垣町東芦田)に生まれる。 |

|
桃山風御殿様式の唐門で、宝暦9年(1760年)の大火で金沢城の大半が消失するも、彫刻された2頭の龍が水を呼び類焼をまぬがれたと言い伝えられている。 彫刻は1本の釘も使用せず名工の作とされるも作者不詳。 |