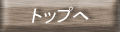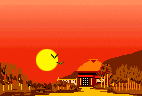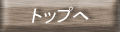『奥の細道』 〜北陸〜
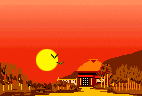
〜弥彦神社〜
国道402号で新潟県を日本海に沿って行くと、弥彦山がある。

弥彦山の東の麓に弥彦神社がある。

弥彦神社は越後一の宮。社殿は弥彦山を背景にして建てられている。
元禄2年(1689年)7月3日、芭蕉は新潟を立ち、弥彦大明神に参詣。
三日 快晴。新潟を立。馬高ク、無用之由、源七指圖ニ而歩行ス。申ノ下刻、彌彦ニ着ス。宿取テ、明神ヘ参詣。
『曽良随行日記』
弥彦神社に芭蕉の句碑があるかと聞いてみたら、弥彦神社にはないが、弥彦競輪場の隣りの宝光院というお寺にあるということだった。
宝光院の句碑

荒海や佐渡によこたふ天河
この句は出雲崎で詠まれたものだが、他に句碑にするのに適当なものが無かったのだろう。
句碑の文字は弥彦神社の庄本光政宮司が揮毫したもの。
句碑はなぜ弥彦神社ではなく、宝光院にあるのだろう。
安永2年(1773年)9月、加舎白雄は弥彦山を句に詠んでいる。
寛政3年(1791年)5月4日、鶴田卓池は弥彦に泊まり、弥彦神社を訪れている。
弥彦 宿問屋次郎右ヱ門
弥彦山大明神
此間渡し三ケ所有テ迷道多し
文化3年(1806年)、岩間乙二は弥彦神社を訪れている。
文化11年(1814年)8月末、十返舎一九は松本を出立、越後に来遊。
あかづかより一りばかりゆきていなじま、それより三りほどすぎてやひこのやしろ、とうごくのいちのみやにて、あまのかぐ山のみことをまつる。けんめいてんわうわどう二ねんのすいじやくなりとかや。しやれう五百石なり。けいだいに、まつしやおほし。
尊さはみな人の目に立杉の
青幣(あをにきて)なる弥彦(いやひこ)のやま
「越後路之記」
嘉永5年(1852年)2月15日、吉田松陰は弥彦神社を参拝。
十五日 翳。岩室を發す。石瀬を過ぎて彌彦に出で、彌彦大明神を拝す。是れを越後の一の宮と爲す。天照大神の曾孫某を祀る。
元禄2年(1689年)7月4日、芭蕉は西生寺を経て出雲崎に行く。
弥彦山の中腹に西生寺がある。

西生寺の案内は無いかと聞くと、拝観券と一緒になっているから、買わないと駄目だと言われた。西生寺を拝観するつもりはないので、諦めた。
『奥の細道』 〜北陸〜に戻る