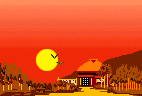『奥の細道』 〜東北〜
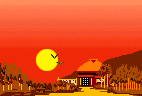
〜「名蹟 袖の渡」〜
石巻市住吉町の旧北上川沿いに大島神社がある。

大島神社

大島神社は延喜式内社。
「陸奥國牡鹿郡 大嶋神社」とある。
大島神社に「名蹟 袖の渡」の碑があった。

昔牛若丸が京より下りて平泉へ赴く道中この渡し舟に乗った時舟賃の代に片小袖を切って舟頭に與えたという傳説から袖の渡と呼ばれたのである。
昭和29年(1954年)8月1日、松下正一建立。
「袖の渡」は、それ以前からの歌枕であった。
みちのくの袖のわたりのなみだ川こころのうちに流れてぞ住む
『新後拾遺和歌集』(相模)
泪川浅きせぞなきみちのくの
|
袖の渡に淵はあれども
| 行家
|
元禄2年(1689年)5月10日(新暦6月26日)、芭蕉は日和山を下りて、「住吉ノ社」に参詣、「袖ノ渡リ」を見ている。
日和山と云ヘ上ル。石ノ巻中不レ残見ゆル。奥ノ海(今ワタノハト云う)・遠嶋(としま)・尾駮(おぶち)ノ牧山眼前也。真野萱原も少見ゆル。帰ニ住吉ノ社参詣。袖ノ渡リ、鳥居ノ前也。
『曽良随行日記』
「住吉ノ社」が大島神社である。
石巻街道は、仙台城下と石巻を結ぶ道で、この街道から北部への道として、涌谷・登米道、気仙道が分かれていました。
金花山道は、石巻から山鳥に至る道で、金華山への参詣の道として利用されました。
一関街道は、石巻から登米を経て一関(岩手県)に至り奥州街道と接続する道でした。
翌11日、芭蕉は石巻から一関街道を登米へ向かう。
天明6年(1786年)8月15日、菅江真澄は「袖の渡」のことを書いている。
こよひの月をまつしまに見むとかねておもふに、はれたるは、ほゐとげたるおもひしていでるに、有隣よんべのかへしとて、
思ひ出は又とめこかし庭せはみかきの萩のいろうすくとも
かくいへり、相模のうたと聞へしは、
みちのくの袖のわたりのなみた川こゝろのうちになかれてそすむ
かゝるところは、此すみよし(大島神社)みまへのわたりといひ、桃生郡横川村に衣川の裾に、袖の山、袖の渡、あるもにつかはし、又あふく川の辺、藤湯の渡をいふといへり。
天明6年(1786年)9月13日、菅江真澄は「袖の渡」を訪れた。
まづ大島の神(住吉をいう)にぬさとる。此北上のすそを。袖の渡といふ。あなたのきしを、みなとといふ。川づらのやにたく火は、星ほたるのごとし。そのあたりより、ふねよばふたび人の声、きぬたの音に、夜さむの衣しられたり。鮭とるあごのふね、あまたささと、波うちわけて、をしありくに、かひやられたるなみは、こがね、しらかねをくだきてのぼるやうに、そこの石ふしのすみかまで、あらわれたる月のくまなきに、
長月のなにおふ月を旅衣袖の渡にやとしてそ見る
つゝむにもあまるこよひのうれしさは、袖のわたりの月見てそしる
昭和3年(1928年)7月25日、荻原井泉水は「袖の渡」を見ている。
この袖のわたりというのは、私は昨日案内されて見た。石の巻の町のうち、住吉町という所で、北上川の渡船場である。架橋の出来ぬうちは半島への交通は皆この渡しに依ったものであろう。今はただ町のちょっと、場末という感じである。
『奥の細道』 〜東北〜に戻る