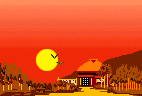『奥の細道』 〜東北〜
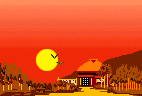
〜芭蕉翁一宿之跡〜
国道342号で登米大橋を渡り、登米の町に入る。

北上川に架かる登米大橋

今の北上川の渡し場は登米の向う岸にある日根牛という村の北のはずれから登米の荒町にかかっておる。昔の渡し場は日根牛の中ほどから三日町にかかっておった。今その渡しの跡を中船場というておる。芭蕉時代には無論中船場に渡しがあった。(石の巻から登米へ来るには、是非ともこの渡しを渡らねばならぬ。)
登米市登米町寺池三日町の北上川堤防の上に「芭蕉翁一宿之跡」の碑があった。
「芭蕉翁一宿之跡」の碑

元禄2年(1689年)5月11日(新暦6月27日)、芭蕉は石巻を立ち、平泉へ赴こうとして、北上川沿いに登米(登米郡登米町)へ至り、その夜は登米で宿泊した。そして翌12日、一関へ向かったのである。芭蕉に同行した曽良の『旅日記』には登米の状況を「戸いま(伊達大蔵)、儀左衛門宿不レ借、仍検断告テ宿ス。検断庄左衛門。」『おくのほそ道』では、その前後を含めて、
……(石巻)宿からんとすれど、更に宿かす人なし。漸まどしき小家に一夜をあかして、明れば又しらぬ道まよひ行。袖のわたり・尾ぶちの牧・まのゝ萱はらなどよそめにみて、遙なる堤を行。心細き長沼にそふ(う)て、戸伊摩と云所に一宿して、平泉に到る。
と述べている。登米の「宿借サズ」を石巻に仮託しているが、北上川を遡って、未知の奥深くわけ入る心細い旅の情緒があふれていて、すぐれた行文に結晶している。
登米は伊達家の一門伊達式部(二万一千石)の城下町である。曽良の『旅日記』の「儀左衛門・庄左衛門」は不明であり、「宿不借」の詳細も知られていない。
河東碧梧桐の六朝風の書体の「芭蕉翁一宿之跡」の碑は、もと検断屋敷跡に建てたものである。北上川の堤防工事で屋敷跡が堤防の一角となってしまったのである。碧梧桐は書でも一家をなしており、この碑は『おくのほそ道』関係の碑の中でも注目すべきものの一つであろう。登米には碧梧桐門下の新傾向の俳人菅原師竹・安斎桜塊子が住んでおり、碧梧桐は『三千里』の旅の途中、10日ほど(明治39年11〜12月)この地に滞在するなど、登米とは深いゆかりがあったのである。
高倉勝子美術館の庭に「師竹・桜塊子」の句碑がある。

舌に残る新茶一露や子規
| 師竹
|
|
晩学静か也杉は花粉を飛ばす
| 桜塊子
|
師竹・桜塊子略歴
菅原師竹 本名は賢五郎。文久3年8月、若柳町伊藤に生れ、登米の菅原家を継いだ。明治大正初期に中央俳壇に輝き、一頭地を抜いた存在であった。書画に秀れ、その作品は大家の風に迫り、諸多の趣味に於ても素人の域を脱した。桜塊子編『師竹句集』がある。大正8年3月24日、歿。享年58。
安斎桜塊子 本名千里。明治19年2月7日、登米に生れ、17歳より師竹と倶に句作に耽り、自由律句誌『海紅』に拠る。作句並に評論・随筆等不断の活躍をつづけ、句集『閭門の草』、随筆集『山に祈る』があり、未刊の稿に『クイ音』(※クイ=「木」+「音」+「戈」)がある。昭和28年12月12日、歿。享年67歳。
碧梧桐は明治39年(1906年)11月23日から12月2日まで登米に滞在した。
十二月一日。天気不定。風なお寒し。
芭蕉が元緑二年五月十三日この登米へ来て一宿したという事は奥の細道で明らかであるが、どういう家へ泊ったかという事は漠として繹(たず)ね難い。ただ口碑が二つ残っておる。
『奥の細道』に「十二日平泉と心ざし」、その翌日「戸伊摩と云所に一宿して」とあり、13日に登米で宿泊したと考えられていた。
三日町に蓮沼某というこの地の名主があった。芭蕉は同家をたよって一泊したが、芭蕉の出立後、その名を始めて知って、主人も後悔したという。かつて同家の倉の中から「海山もゆるぎ入るるや夏坐敷」と書いた芭蕉の短尺が出たこともあるというのがその一。
予思うに、当時のこの町はどういう有様であったかは知らぬが、往来の僧形として石の巻では宿を貸さなかった位であるから、あるいはこの地では名主の厄介になったかもしれぬ。が、ただ疑わしいのは登米という成字のあるにも関らず、「戸伊磨」と万葉仮名をあてはめており、それも「とよま」を「といま」となった俗称に因っておることである。
何れ旅の物うさに処の名など十分問い正さなかったかもわからぬが、名主を勤める位の者に土地の名を知らぬという事はないように思う。また旅中精査の暇がないため確言は出来ぬが「海山も」の句は後世月並俳人の口吻で芭蕉の句とは思われぬ。
昭和3年(1928年)7月25日、荻原井泉水は登米で桜塊子君を訪ねた。
登米では桜塊子君を訪ねた。芭蕉は戸伊摩と書いている。そういう風に聞こえたまま字を宛てたのだろうが、昔から登米と書いてトヨマと詠んだものらしい。今日では誤ってトメと読む人が多くなり、仕方なくて、トメ(登米)郡、トヨマ(登米)町と読み分けることにしているという。芭蕉が泊った家というのは、北上川の橋を渡って二、三町来て、郵便局の角を曲がった所に一宿庵という名の家がそれだと伝えられていたが、それも焼けてしまって、「山も庭もうごき入るるや夏坐敷」という句碑だけが残っているという。
『随筆芭蕉』(平泉に到る)
大田原市の浄法寺桃雪邸跡に「山も庭も動き入るるや夏座敷」の句碑がある。
『奥の細道』 〜東北〜に戻る。