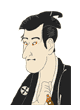『奥の細道』 ~東北~
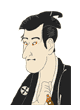
『陸奥鵆』[無都遅登理 五]②
元禄9年(1696年)、天野桃隣が芭蕉三回忌にあたって『奥の細道』の跡をたどった紀行文。
元禄10年(1697年)8月、素堂跋。
天野桃隣は白河に出て、関山に登っている。
成就山光明院満願寺

此所山を越、白河に出、宗祇戻しへ掛リ、加嶋・桜が岡・なつかし山・二形山、何(いづれ)も順道也。是より関山へ登ル。峯に聖観音、聖武帝勅願所、成就山 満願寺、坊の書院よりの見渡し白河第一の景地也。
奥の花や四月に咲を関の山
此所、往昔の関所と也。本道二十丁下りて、城下へ出、関を越る。
気散じや手形もいらず郭公
石川の滝(乙字ケ滝)

須ヶ川、此所一里脇、石川の滝アリ。幅百余間、高サ三丈に近し。無双の川滝、遙に川下ヨリ見れば、丹州あまのはしだてにひとし。
○比も夏滝に飛込こゝろ哉
桃隣は小名浜からいわき湯本温泉を訪れている。
小名浜ヨリ二里来て湯本アリ。山は権現堂、梺は町家、温泉数五十三、家々の内に有。勝手能諸事自由にて、近国より旅人不絶。
黒塚

二本松城下にさしかゝり、亀が井町より半里、阿武隈川の川端に、彼黒塚有、辺は田畑也。此あたりをさして安達原と云。
○塚ばかり今も籠るか麦畠
文字摺の石

福嶋より山口村へ一里、此所より阿武隈の渡しを越、山のさしかゝり、谷間に文字摺の石有り。
○文字摺の石の幅知ル扇哉
瑠璃光山医王寺

一里行、左の方径より左葉野と云所、二里分入、瑠璃光山医王寺。宝物品々有、中に義経の笈、弁慶手跡大般若アリ。
桃隣は医王寺から佐藤庄司の旧跡を訪れ、句を詠んでいる。
大鳥神社

祭神 佐藤基治侯継信侯・忠信侯
佐藤庄司旧跡、丸山城跡アリ。南殿桜夜の星是名水の井也。庄司墓所、一門石塔、次信・忠信石塔有。
○星の井の名も頼母しや杜若
○丸山の構も武き若葉哉
桃隣は佐藤庄司の旧跡から飯坂を経て桑折へ。
桃隣は桑折から藤田村(現国見町)を経て義経の腰掛松へ。
義経の腰掛松

是ヨリ藤田村へかゝり、町を出離て、左の方へ二丁入、義経腰掛松有。枝葉八方に垂、枝の半バ地につき、木末は空に延て、十間四方にそびえ、苺(こけ)の重り千歳の粧ひ、暫木陰に時をうつしぬ。
○唐崎と曽根とはいかに松の蝉
桃隣は義経の腰掛松から伊達の大木戸へ。
長坂道

経塚山此所なり。又海道へ出るに、国見山高クさゝえ(へ)、伊達の大木戸構(かまへ)きびしく見ゆ。
このページのトップに戻る
『奥の細道』 ~東北~に戻る