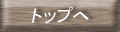私の旅日記〜2004年〜
真間山弘法寺〜句碑巡り〜

亀井院の裏山が真間山で、真間山弘法寺(ぐほうじ)がある。

日蓮宗本山である。
真間山弘法寺
天平の昔、行基菩薩が来錫(らいしゃく)し、真間の地に語り伝わる手児奈の霊を供養して一宇を建て、「求法寺(ぐほうじ)」と称したが、その後、空海(弘法大師)によって七堂伽藍が造営され、「真間山弘法寺」と改められたが、本寺の起こりと伝えている。
境内には、水原秋桜子、富安風生の句碑等が存する。
石段を登ると、仁王門がある。

安永7年(1778年)8月14日、横田柳几は関東三社詣での途次、弘法寺に参詣している。
日蓮宗真間山弘経(ママ)寺へ詣庭前に古樹三株あり所謂真間のもみち是なり枝の内一茎二葉稀に有外の樹より紅葉遅しと云