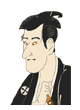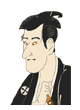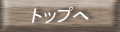石川啄木ゆかりの地
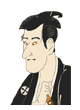
啄木小公園〜石川啄木の像〜
「ラビスタ函館ベイ」から啄木小公園へ。

啄木小公園
この辺りは、かつて砂丘があって、ハマナスが咲き乱れていた。啄木が好んで散歩した所であり、歌集『一握の砂』に「砂山の砂に腹這ひ初恋のいたみを遠くおもひ出づる日」と歌われている。詩集『あこがれ』を左手に持ち、もの思いにふける啄木の座像(本郷新作)は、昭和33年(1958年)に建てられた。隣の石碑は、後年啄木の墓を訪れた詩人西条八十が啄木に捧げた自筆の歌碑である。
啄木が函館に来たのは明治40年(1907年)5月のことで、7月には離散していた妻子を呼び寄せ、久しぶりに親子水入らずの生活を営んだ。
弥生小学校の代用教員を経て、函館日日新聞の記者となって間もなくの8月25日、函館は未曾有の大火に襲われた。
新聞社も焼失し、啄木は職を求めて、妻子を残したまま函館を去った。
函館滞在の4か月余りは、彼の一生のうちで、最も楽しい期間であったといわれている。
函館市
啄木の座像

函館文学館にも石川啄木の像がある。
台座に啄木の歌が刻まれている。

潮かをる北の浜辺の
|
砂山のかの浜茄子よ
|
今年も咲けるや
|
『一握の砂』収録の歌である。
西条八十が啄木に捧げた自筆の歌碑