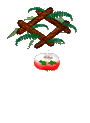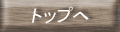2017年〜北海道〜
トラピスチヌ修道院〜聖ミカエル〜
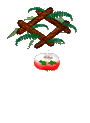
鹿部温泉から函館に向かう。
トラピスチヌ修道院に立ち寄ってみた。
厳律シトー会天使の聖母トラピスチヌ修道院
厳律シトー会天使の聖母トラピスチヌ修道院は、明治31年(1898年)、フランスのウプシーにある修道院から8名の修道女が来たのが始まりである。キリスト教伝道のためには、修道院の精神的援助が必要であると、函館教区長ベルリオーズ司教が要請していたものであった。
草創期の修道女たちの生活は困難を極め、それを見かねたフランスから、引き揚げが伝えられるほどであった。
現在の建物は大部分が大正14年(1925年)の火災後、昭和2年(1927年)に再建されたものである。
函館市
聖ミカエル

聖ミカエルは大天使です。
悪魔が神に反逆した時、「ミ・カ・エル」(ヘブライ語で神のように振舞うものは誰か、という意味)と叫びながらこれを破り、神に忠誠を尽くしました。
日本にキリスト教を伝えた聖フランシスコ・ザビエルは聖ミカエルを日本の保護者と定めました。
私達も、悪魔の誘いに負けることなく、日々正しく生きるよう、聖見返るの保護を求めて祈りましょう。
第二次世界大戦の間、修道女達は、函館の町と津軽海峡を往く船が戦火から守られるよう、聖ミカエルの保護を願って祈りました。この像はその時の御加護を感謝して1953年、建立されたものです。
フランスから贈られた元の像は、テラコッタ製でしたが、風雪で損傷したため、1986年、ブロンズで鋳造し直されました。

慈しみの聖母マリア