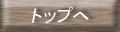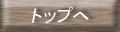2009年〜山 梨〜
大善寺〜薬師堂〜

甲州市勝沼町勝沼に大善寺(HP)という寺がある。

真言宗智山派の寺である。
養老2年(718年)、僧行基は夢の中に右手に葡萄を持った薬師如来が現れたそうだ。行基が夢の中に現れた薬師如来像を刻んで安置したのが柏尾山大善寺という。
拝観料は500円。
私の他に拝観する人はいなかった。
大善寺山門

寛政10年(1798年)、再建。
勝沼町指定建造物である。
山門の紅梅

石段を登ると、薬師堂がある。

弘安9年(1286年)、建立。
山梨県で一番古い建物で、国宝である。
ちなみに山梨市の清白寺仏殿も国宝。
山梨県の国宝建造物は、この2つだけである。
月光菩薩立像

嘉禄3年(1227年)、仏師蓮慶により製作された。
国の重要文化財である。
本尊薬師如来は秘仏。5年に一度、開帳する。
文明19年(1487年)、道興准后は大善寺に泊まっている。
かし尾といへる山寺に一宿し侍りければ、かの住持のいはく、後の世のため一首を残し侍るべきよし頻りに申し侍りければ、立ちながら口にまかせて申し遣しける。かし尾と俗語に申し習し侍れども、柏尾山にて侍るとなむ。
蔭頼む岩もと柏おのづから一よかりねに手折りてそしく
大善寺東参道の崖の上に「芭蕉翁甲斐塚」があった。

蛤のいけるかひあれ年の暮
出典は『薦獅子集』。
蛤のいけるかひあれ年の暮
一書に云、山家集に
今ぞしる二見の浦の蛤を
かひあわせとておほふ也けり
愚考、すまの巻の心はへを取ての句なり。海士どもあさりして、貝一物もてまゐれるをめしいでゝ御覧ず。浦にとしふるさまなど問はせ給ふ。さまざまやすげなき身の上を申す。そこはかとなくさへづるも心の行衛は同じこと、何か異なると哀に見給ひ、御衣どもかづけさせ給ふを、いけるかひありと思ヘり。
元禄5年(1692年)12月の句である。
芭蕉翁甲斐塚
「蛤の生ける甲斐あれ年の暮れ」 芭蕉
この碑は、宝暦12年(1762年)10月に藤井村の草々庵梅童(1701〜1781)が父梅馬の遺志を継ぎ建立したもので、合わせて『俳諧甲斐塚集』が撰集され、「霜を出て霜より白し塚の月」の梅童の建立句が伝えられている。梅馬(〜1757)は名を渡辺武右衛門といい、守墨庵柳居や弟子の門瑟と親交があり、蕉門の柳居の流れを甲斐に伝えた先駆者。
また、この碑は県内に数多くある芭蕉句碑の中で最も古いものである。
勝沼町教育委員会
宝暦7年(1757年)、梅馬は佯死して梅童と改めた。『冨士井の水』(三城編)刊。
安永10年(1780年)3月4日、86歳で没。
梅馬の句
平成17年(2005年)11月1日、勝沼町は塩山市および大和村と合併して甲州市となった。
2009年〜山 梨〜に戻る