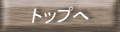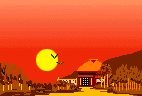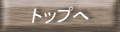私の旅日記〜2007年〜
増上寺〜東京タワー〜
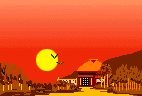
都営地下鉄三田線御成門駅から日比谷通りを歩き、増上寺(HP)へ。

御成門は増上寺の北方馬場にあった裏門の別称で、将軍が増上寺に参詣する際、この裏門がもっぱら用いられたので、御成門と呼ばれるようになったそうだ。
東京プリンスホテルの駐車場脇に移転して現存している。
御成門

東京プリンスホテルに有章院霊廟二天門がある。
有章院霊廟二天門

国の重要文化財
有章院は第7代将軍徳川家継の院号。有章院霊廟は第8代将軍徳川吉宗が建立。空襲で二天門を残して焼失した。
増上寺は江戸三十三観音第21番札所。
また寛永寺などと共に徳川家菩提寺の1つ。
明徳4年(1393年)、武蔵国豊島郷貝塚に増上寺創建。
慶長3年(1598年)、芝に移転。
三解脱門(三門)

元和8年(1622年)、建立。国の重要文化財
大殿

昭和49年(1974年)、再建。
東京タワーが見える。
増上寺は浄土宗大本山である。
関東十八檀林のひとつ。
水盤舎

榎本其角は増上寺の晩景を句に詠んでいる。
鐘楼堂

大梵鐘は延宝元年(1673年)に完成。
今鳴るは芝か上野か浅草か江戸七分ほどは聞える芝の鐘
元文2年(1737年)5月20、佐久間柳居は江戸を立って箱根に向かう。途中で増上寺の鐘を句に詠んでいる。
僧(ママ)上寺を見やりて
舟からは遠寺の鐘や夏木立
江戸三大名鐘の1つ。江戸三大名鐘は芝(増上寺)、上野(寛永寺)、浅草(浅草寺)とも言うが、はっきりしない。
鐘がなる春のあけぼのヽ増上寺 万木
芝公園に句碑がある。
増上寺旧方丈門(黒門)

増上寺方丈の表門であった旧方丈門。黒漆塗であったために黒門とも呼ばれた。
現在は増上寺通用門。
明和8年(1771年)4月29日、諸九尼は増上寺に参詣している。
廿九日 増上寺に参るに、めざましきまでに、堂塔甍をならぶ。この日松露庵、雪中庵をも尋行て、旅の心もなくかたらひ侍りぬ。
東京タワーのライトアップ

手前は「レストランプリンスビラ」。
2/18(日)東京マラソン交通規制

私の旅日記〜2007年〜に戻る