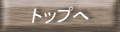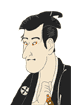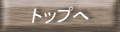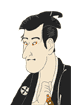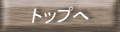私の旅日記〜2013年〜
芝丸山古墳〜伊能忠敬測地遺功表〜
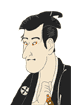
東京都港区芝公園に芝丸山古墳がある。

芝公園から見る東京タワー

東京都指定史跡 芝丸山古墳
全長106メートル前後、後円部径約64メートル、前方部前端幅約40メートル、くびれ部幅約22メートルほどの、都内最大級の規模をもつ前方後円墳である。標高約16メートルの台地端に位置し、前方部を南々西に向けている。
江戸時代以降、原形はかなり損じられており、とくに墳頂部や後円部西側は削られてしまっている。明治31年に、日本考古学の先駆者坪井正五郎博士によって調査されたが、すでに後円部中央に位置したと考えられる主体部(埋葬施設)は失われており、遺体や副葬品なども不明である。なお、埴輪を伴うことは知られている。
前方部が狭く低い形態や、占地状態などから5世紀代の築造とみられており、そのころ、附近の低地の水田地帯に生産基盤をもち、南北の交通路をおさえていた、南武蔵有数の族長の墓だったと考えられる。
平成2年12月27日 再建
東京都教育委員会
伊能忠敬測地遺功表

伊能忠敬先生は1745年(延享2年)上総國に生れて下総國佐原の伊能家を嗣ぎ村を治めて後50歳のとき江戸に出て高橋至時のもとで天文暦數の學を究めた。先生の卓見と創意とによる測地測量は1800年の蝦夷地奥州街道の實測を始めとして全國津々浦々にまで及び1818年(文政元年)江戸八丁堀で74歳をもって歿するまで不屈の精神と不斷の努力とによって續けられわが國の全輪郭と骨格とが茲に初めて明らかにされるに至った。
その偉業は引きつがれて1821年大中小の大日本沿海輿地全圖が完成せられその精度の高きことは世界を驚嘆せしめた程であり参謀本部測両局の輯成二十万分一地圖は實にこの伊能圖を骨子としたものである。
東京地学協會はその功績を顕彰して1889年この地に贈正四位伊能忠敬先生測地遺功表を建設したが不幸にして第二次大戦中に失われるに至った。仍つて今回各方面の協賛を得てこの碑を再建した次第である。
1965年5月
社団法人 東京地学協會 會長 細川護立
丸山西頂部に大野伴睦の句碑にあった。

鐘がなる春のあけぼのヽ増上寺 万木
碑文揮毫 鳩山 薫
昭和39年(1964年)5月29日、伴睦は73歳で没。
昭和39年(1964年)9月、句碑建立。
私の旅日記〜2013年〜に戻る