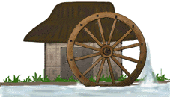下 町〜墨田区
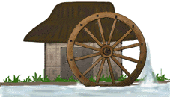
向島百花園〜御成座敷〜
1年半振りに向島百花園へ。

向島百花園は文化・文政時代、佐原鞠塢(きくう)によって開設された。百花園の名は「梅は百花のさきがけ」という意味で、酒井抱一が命名したという。亀戸の梅屋敷に対し「新梅屋敷」と呼ばれたりしたそうだ。
酒井抱一(1761−1828)は江戸後期の画家で、狂歌・俳諧なども嗜む。代表作「夏秋草図屏風」。
佐原鞠塢(きくう)は天明年間に仙台から江戸に出た。日本橋住吉町に骨董店を開き、北野屋平兵衛と称する。当時、亀田鵬斎と交流があった。本所に隠居してから菊屋宇兵衛、略して菊宇と称した。それを鵬斎の助言によって鞠塢と改めたそうだ。寺島村に多賀屋敷と呼ばれていた土地を得て、百花園を開いた。
加藤千蔭が「お茶きこしめせ、梅干も候ぞ」と書いた掛け行燈があったそうだ。
加藤千蔭(1735−1808)は江戸後期の国学者・歌人。本姓、橘氏。著「うけらが花」など。
門前の婆々が榎の涼し過
| 一茶
|
|
連歌めせめせ萩も候
| ゝ
|
鞠塢は道彦門の四天狗と言われた俳人。道彦も仙台の人である。
文政9年(1826年)、鞠塢は『墨多川集』刊行。
すみだ川くれぬうちより朧也
| 一茶
|
|
すみだ川の露や三月十五日
| 菊塢
|
天保3年(1832年)8月29日、鞠塢(きくう)没。70歳。
鞠塢(きくう)から8代目の佐原滋元(しげもと)氏が百花園内で茶店「茶亭さはら」を営業している。「お茶きこしめせ、梅干も候ぞ」と書いた掛け行燈は、今でも売店の店先に掛かっているそうだ。
向島百花園に入ると、亀田鵬斎「墨沱梅荘記」の碑があった。
亀田鵬斎「墨沱梅荘記」の碑

墨沱の瀕(ほとり)葛陂の傍、荒圃鋤かれて新園成る。之に梅一百株を植う。毎歳立春伝信の候より二月啓蟄の節に捗(わた)り、樹々花を着つけ満園雪の如し。之を望めば則ち白浪空に翻るが若く、蓬莱の銀闕水底に在りて近づくべからざるが若きなり。
亀田鵬斎「墨沱梅荘記」
百花園は梅の名所だったようである。
「墨沱梅荘記」は文化11年(1814年)2月15日に書かれたもの。
亀田鵬斎(1752−1826)は江戸後期の儒者。
角田川あみして秋の句を得たり 鵬斎
下 町〜墨田区に戻る