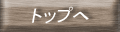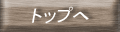私の旅日記〜2011年〜
難波別院南御堂〜碑巡り〜

大阪市中央区久太郎町4丁目に難波別院南御堂(HP)がある。

難波別院南御堂

真宗大谷派の寺である。
本堂の左手に獅子吼園がある。
獅子吼園に芭蕉句碑があった。

旅に病で夢は枯野をかけまはる
出典は『芭蕉翁行状記』(路通編)。
『笈日記』(支考編)には「かけ廻る」とある。
天保14年(1843年)、芭蕉の百五十回忌に建てられたようである。
この句は芭蕉の臨終の句の一つで、この大阪の地で吟ぜられたものである。
芭蕉は元禄7年(1694年)秋、伊賀から門人達に迎えられて大阪に着いたが、滞在中に病気になり、養生のかいもなく10月12日この南御堂前で花を商う花屋仁左衛門の屋敷で51歳を一期として旅の生涯を閉じた。
この句碑は、後世天保の俳人達によって建てられたものである。
当南御堂では、芭蕉を偲んで毎年芭蕉忌が勧修され、法要の後盛大に句会が催されている。
南御堂難波別院
昭和4年(1929年)11月8日、荻原井泉水は南御堂で芭蕉の句碑を見ている。
三方に築地の石を高くし、西北の方には土堰を築き、霧島躑躅が植えてある。その北の土堰に続いて、境内の方に岡のように土を寄せかけて作ったところを、俗称やまという、その中腹に高さ五尺もあろう、句碑が立っている――「旅に病てゆめは枯野をかけめぐる はせを」。やまの下に柵を作って近づく事が出来ないから、年代などは解らない。門前の通りは、成程、道路工事の取払最中である。
山口誓子の句碑があった。

金色の御堂に芭蕉忌を修す
昭和37年(1962年)10月、山口誓子は南御堂を訪れている。山口誓子は南御堂を訪れている。
昭和40年(1965年)、山口誓子は南御堂に芭蕉の句碑を訪ねた。
「旅に病て」の句碑は、南御堂(難波別院)の北築山にずっと前から建っていたと云う。御堂前に広い道路が出来たとき、その御堂筋の東側、車道と車道の中間地帯に出て来た。昭和九年のことである。
それが昭和三十七年、再び南御堂の境内、北西の隅に返された。本来在るべきところに帰ったのだ。私もその式典に列した。
自然石に
旅に病てゆめは枯野をかけまはる
と彫られている。
「旅に病て」をどう読む。「病んで」か「病みて」か。「かけ廻る」を「かけまはる」と読んでいいか。
私は「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」と読みたい。それが一番調子がよい。
(中略)
私はこの句を、芭蕉が生涯の終りに到り着いた最高の句と思っている。句碑の書はこの句に負けている。それを書いた脇坂窓明は南御堂列座。歌人であった。
昭和44年(1969年)10月、山口誓子は南御堂を訪れている。
南御堂
芭蕉忌にビルのガラスの絶壁よ
芭蕉忌に垂らす大福山水畫
『不動』
阿波野青畝の句碑もあった。

翁忌に行かむ晴れても時雨れても
南御堂前の御堂筋緑地帯に「花屋仁左衛門宅跡」がある。

此附近芭蕉翁終焉ノ地ト傳フ
昭和9年(1934年)3月、大阪府建立。
『芭蕉翁繪詞傳』愚按には、「花屋仁右衛門」とある。
宝暦6年(1756年)11月2日、鳥酔は「花屋仁右衛門」跡を訪ねている。
○はせを翁僊化の地 花屋仁右衛門かかし座敷今ははりま屋勘兵衛住
霜降月二日潤二子に伴れて祖翁遷化し給たる南御堂の舊宅を尋ぬ彼病床の吟に夢は枯野とありしその寐姿にうかみぬるまゝに今のあるしへ囁くのみ
來て見れは夢のすかたは火燵哉
文化6年(1809年)、茅渟奇淵は南御堂前の芭蕉終焉の地で花屋庵を営む。
「私の旅日記」〜2011年〜に戻る