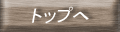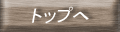私の旅日記〜2011年〜
浮瀬亭俳跡蕉蕪園〜碑巡り〜

大阪市天王寺区伶人町に大阪星光学院がある。

大阪星光学院に蕉蕪園がある。
浮瀬亭俳跡蕉蕪園
新清水寺の北隣りにあった浮瀬は、江戸時代大阪を代表する料亭であった。当初、清水の茶屋とも晴々亭とも呼ばれていたが、所蔵するアワビ貝の奇盃「うかむ瀬」が有名となるにつれて、料亭の名もいつしか浮瀬と呼ばれるようになったようだ。
元禄7年(1694年)9月26日、この茶店で芭蕉が「この道や行人なしに秋の暮」を発句に、支考ら10人と半歌仙を巻き、旅懐と題して「松風の軒をめぐりて秋暮れぬ」の句を、茅渟奇淵が句碑として建立。裏面に不二庵二柳が松風碑賛を記した。また芭蕉を追慕する念の篤かった蕪村も浮瀬の句を2句残した。
芭蕉「所思碑」

此道を行人なしに秋の暮
元禄7年(1694年)9月26日、浮瀬亭で所思と題して詠んだ半歌仙の発句である。
書は出光美術館蔵「曲翠宛書簡」(9月25日付)にある芭蕉の真跡である。
「此道や」の初案である。
昭和58年(1983年)5月24日、芭蕉二百九十年忌追善に大阪星光学院高等学校二十八期生が建立。
芭蕉「旅懐碑」

此秋は何で年よる雲に鳥
元禄7年(1694年)9月26日、浮瀬亭で詠んだ句である。
書はお茶の水女子大学名誉教授井本農一先生の揮毫による。
昭和59年(1984年)3月1日、芭蕉二百九十年忌追善に大阪星光学院高等学校二十九期生が建立。
蕪村「うかぶ瀬」句碑

うかぶ瀬に沓並べけり春のくれ
|
|
うかふ瀬に遊ひてむかし
|
栢莚がこのところにての狂句を
|
おもひ出て其風調に倣ふ
|
|
小春凪真帆も七合五勺かな
|
昭和57年(1982年)11月1日、蕪村二百年忌追善に大阪星光学院高等学校二十七期生が建立。
「半歌仙」碑

此道や行人なしに秋の暮
| ばせを
|
|
岨の畠の木にかゝる蔦
| 泥足
|
|
月しらむ蕎麦のこぼれてに鳥の寐て
| 支考
|
|
小き家を出て水汲む
| 游刀
|
|
天気相羽織を入て荷拵らへ
| 之道
|
|
酒で痛のとまる腹癖
| 車庸
|
元禄7年(1694年)9月26日、浮瀬亭で詠んだ半歌仙である。
表面の書は東京大学総合図書館所蔵竹冷文庫の泥足『其便』下を複写拡大したものである。
平成5年(1993年)10月12日、浮瀬亭俳跡蕉蕪園開園10周年記念、芭蕉三百年忌追善に大阪星光学院高等学校三十九期生が建立。
芭蕉「松風碑」

松風の軒をめぐりて秋くれぬ
出典は『泊船集』(風国編)。「大坂清水茶店 四郎右衛門にて」と前書きがある。
寛政12年(1800年)秋、茅渟奇淵建立。
碑陰に不二庵桃居の「正風宗師松風碑賛」が記されている。
をしてるやよし芦のなに波江に
|
影うかふせの昔ゆかしき
|
いしふみの石まつかせの松
|
こゝに翁のあとは絶せし
|
|
芭蕉三世劣孫 不二庵桃居誌
|
茅渟奇淵は菅沼氏、泉州堺の人。大阪に出て二柳の門に学ぶ。
明和8年(1771年)4月8日、蝶夢は桐雨を伴って伏見で舟に乗り、清水の浮瀬亭に上る。
日もくれ竹のふしみの舟にのりて、難波につくに、こゝらしれる人々名残お(を)しまんとて、共に清水のうかぶ瀬といふ酒楼に上りて、
住よしの松から来たか青あらし
西の海づらを見わたして、あの海の限りまでも行んとおもふこゝろ細し。此津の留別とて、
うき草や芦も一夜の居り処 桐雨
「私の旅日記」〜2011年〜に戻る