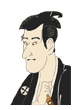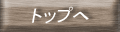私の旅日記〜2015年〜
春徳寺〜時雨塚〜
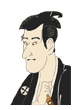
長崎市夫婦川町に春徳寺という寺がある。

春徳寺山門

トードス・オス・サントス教会跡コレジヨセミナリヨ跡
永禄10年(1567年)領主長崎甚左衛門にキリスト教の布教の許しを得たアルメイダは、以後長崎での布教を始めました。甚左衛門の館は、現在の桜馬場中学校の地にあり、その周辺に集落が形成されていました。甚左衛門はガスパル・ビレラ神父にこの地にあった小さな寺院を提供、同12年この寺院を改装して長崎で最初の教会が造られました。同教会には、慶長2年(1597年)にセミナリヨやコレジオも置かれ、活字印刷所なども併設されました。
華嶽山春徳寺

臨済宗建仁寺派の寺である。
本堂の向かいに5基の石碑が並んでいる。

一番右が「時雨塚」。

崎陽門人等合立
芭 蕉 翁 之 塔
元禄12年(1699年)、芭蕉の七回忌に野坡の撰文で長崎一ノ瀬街道に建立。林陀方書。
『諸国翁墳記』に「時雨塚 肥前長嵜ニアリ 宇鹿建」とある。