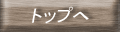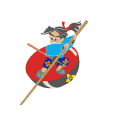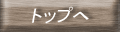2018年〜高 知〜
竜串海岸〜桜浜海水浴場〜
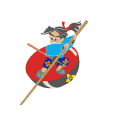
「足摺国際ホテル」から国道321号(サニーロード)を行き竜串海岸へ。
竜串・見残し海岸
この海岸は2000万〜1500万年前の砂岩からなる海食台地で、浸食によってできた怪岩奇岩が続いています。特に見残し海岸では、この地域独特の蜂の巣のように蝕された奇岩が連続しており、その景観は自然の芸術といわれています。一方竜串海岸では、節理の発達した奇岩が競うようにせり出していて、その上を歩くとまるで恐竜の背骨を歩いているかのように感じます。岩の形によって名前がつけられていますが、それは、見残しとはまた違ったユーモアがあります。
武者小路實篤文学碑があった。

貝殻は私の生きていたあかし
|
私が生きていなかったら
|
私の貝殻はあるわけはない
|
怪岩奇岩

化石漣痕

欄間石

昭和39年(1964年)8月17日、高浜年尾は足摺岬及び竜串海岸を旅吟。
八月十七日 足摺岬及竜串旅吟
海底の海胆の生態見しことも
めづらしく蚊帳吊る宿に一泊す
足摺海底館が見える。

危険なので、引き返す。
桜浜海水浴場

こちらからも足摺海底館が見えた。

見残し海岸は、たやすく行ける所ではなかった。
弘法大師が「見残し」たのも無理はない。
高知県は奥が深い。
2018年〜高 知〜に戻る