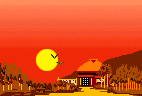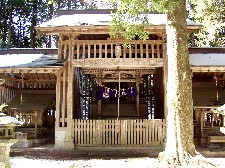『奥の細道』 〜東北〜
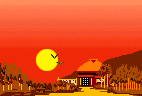
〜白坂境明神〜
金売吉次の墓から国道294号(陸羽街道)を行くと、福島と栃木の県境に白坂境明神がある。

白坂境明神
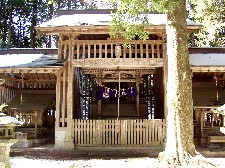
社殿の裏に芭蕉の句碑がある。
国道294号(陸羽街道)を挟んで白坂境明神の反対側に「白河二所ノ関址」の石碑がある。
白河二所ノ関址

石碑の辺りは今朝からの雪で覆われている。
4月下旬には二輪草(にりんそう)が一面に咲くそうだ。
残念ながら、文字ははっきりしない。
白坂境明神に説明が書いてある。
境の明神と二所の関
白河の関は「二所の関」と古来からいわれるとおり二ヶ所にあった。勿来の関といわれた菊多関と共に大和政権が蝦夷対策として設けたもので南北800間に数ヶ所配置された関があった。
白河市旗宿地内の「関の森」は城主松平定信が「古関蹟」と断定し、昭和12年国指定史跡指定となっている。
松平定信は白坂の二所の関(境の明神)を関跡だとするのは間違いであると指摘した。
白川の関は、いづ地にありや知らず。今の奥野の境、白坂宿に、玉津の島の明神の社あるを、古関のあといふはひが事なり。
松平定信『退閑雑記(たいかんざっき)』
芭蕉が旅をした頃、白河の関はどうなっていたのだろう。
廿一日 霧雨降ル、辰上尅止。宿ヲ出ル。町ヨリ西ノ方ニ住吉・玉島ヲ一所ニ祝奉宮有。古ノ関ノ明神故ニ二所ノ関ノ名有ノ由、宿ノ主申ニ依テ参詣。
『曽良随行日記』
奈良・平安初期の国境に男女2神を祀るとされ、下野国住吉神社に中簡男命を祀り関東明神と称し、岩城国玉津島神社に衣通姫命を祀り奥州別神と称し、「二所の関」の由来するところであります。
「下野国住吉神社」とあるが、那須町指定史跡「境の明神」は「玉津島神社」である。
那須町指定史跡「境の明神」

元禄2年、庶民芸術、文化はなやかな頃、芭蕉が曽良を伴い奥州の第一歩を関の明神へとさしかゝり、夕暮れ時、くいなが鳴いていた。
国守の宿をくいなに問おうもの 曽良
芭蕉は須賀川で門人等躬から初めて白河に俳人何云(かうん)の存在を聞く。そこで須賀川の旅篭から書簡を認めた。何云は白河藩士。
初夏の奥州路はうつぎの花が真白にさいてにぎやかな田植え唄がきこえ、やっと奥州に入った心をはずませて旅を続けたことゝ思う。
元禄2年(1689年)4月20日(新暦6月7日)、芭蕉は「関明神」から「奥の細道」に入ったのだが、『奥の細道』には何も書かれていない。
宝永6年(1709年)、明式法師は「白川二所の明神」を訪れている。
柳を見、下野奥州の界に入る。住吉玉津島の神祠をたつ。白川二所の明神とまうすなり。南は壽寶山北は和光山、おのおの額を掲ぐ。昔の關は大田原の北、旗宿と云ふ所なり。
元文3年(1738年)4月20日、田中千梅は松島行脚の途上、「白川二所の明神」を訪れている。
猶行ほとに境明神を拜し白川に至れは奥州の地に足を入関東乃明神奥の明神両社や関東之明神ハ宝壽山奥之明神ハ和光山共ニ黄檗高泉和尚額也
元文3年(1738年)4月、山崎北華は『奥の細道』の足跡をたどって白河関に着いた。
雷雨に辛き目見て漸くたどり。白河の關に着きて。堺の明神の邊(ほとり)に宿かる。堺の明神と申すは。下野と陸奥との堺なり。下野の方は玉津島明神。陸奥の方は住吉明神なり。彼是と句案せしかども。さしも和歌二柱の御神所といへば。白河の關如何なる事を申して。深慮にも叶ひ。又名所にも宜しからんやと。計り難く恐ろしくて。何も申さでぬかつけば。杜鵑聲す。
我が唖(おし)を笑ふか關の不如歸
延享4年(1747年)、横田柳几と武藤白尼は陸奥行脚の帰途、白坂の二所の関を通っている。
白坂を越て二所か関を過るとて
|
境の明神は陸野両国の鎮守にて鳥居も立双ひたり
|
寛政12年(1800年)8月、大江丸は二所の関を訪れている。
下野とむつの国の境を二所が関といへり。両国の神社ならびたちておハす。いづれも玉つしまの神をしづめ奉るのよし、むつの国の太守御国へいで入りの度ごと、此処にこしをとゞめ、餅をきこしめさるゝ加(嘉)例のよし委事はふじや甚左衛門といへる茶店のぬしの物がたり也。こゝ即いにしへ白川のせきのあとゝてうた人の心をとむる所なれ。又ある人のいふ、いにしへの関は四五丁馬手のかたなりしと。
能因にくさめさせたる秋はこゝ
新那須温泉へ。
『奥の細道』 〜東北〜に戻る。