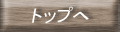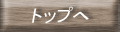五升庵蝶夢

『雲州紀行』(蝶夢)
安永8年(1779年)2月21日、蝶夢が沂風を伴い京を発して出雲に旅立ち、3月23日、出雲大社に参詣、4月5日、須磨に帰り着くまでの紀行。
文政2年(1819年)、『はまちどり』(古声)に収録。
そもこの國にうまれ出たらん人の風雅の道をわきまゆる事、いづれか出雲八重垣のこと葉より出だるはあらずかし、その八雲たつといへる出雲の神にまうでん事、としごろの願ひなりしが、ことし安永八年二月も末の一日、空も霞こめて、雲雀さへづる野の色にうかれて、沂風法師を具して東山の草廬をいづるに、山陽道の古きをたどらんとて、難波のかたへは行かで、油の小路を南へ行くに、竹の林の中に小祠あり道祖神にておはしけるに。
朝がすみたつは首途の宮居かな
| 蝶夢
|
須磨寺より一の谷のかたへ行道は、小砂まじりの山間也
須磨の山うしろや春も松ばかり
| 蝶夢
|
|
所々燒て物うしすまの山
| 沂風
|
明石の大藏谷にとまる。
廿四日、人丸の社にまうづ、此所にて蕉翁の塚供養の千句興行ありしも、二むかしもや、午時ばかりに加古の渡の山李がかくれ家につくに、年ごろのなつかしさいひ出して物語るに、そこらしれる人の多く來りて、行さきはるけき道の程なり。足に灸すへよ、杖の竹きりてと、いたはれば、二日ばかりこの三眺庵にやどる。
三月朔日、かさ目山を跡に、吉備の中山の方へ行、細谷河をわたる
落椿ほそ谷河のなほ細し
| 蝶夢
|
|
谷河やくらき所にすみれ草
| 沂風
|
丹波少將の喜界ケ島より歸路の時、この墓にて卒都婆を造りて、かこたりしありさまも、今のやうにて悲し、吉備津の宮吉備郡眞金町大字宮内に參る、此神垣には神供の釜鳴動して吉凶をしめし給ふ、いちじるき神事あり、釜殿といふ、其神供をかしぐ老女は、國の内にて出る郷里さだまれるとか。
はるかぜにつれてや釜のいさましき
| 蝶夢
|
笠岡小田郡笠岡町ひ着て黒崎屋といふに宿す。
三日、上巳の節とて家毎に桃柳の枝を軒にかざす、あやめこそ軒にふくものを、かの陸奥にあやめふくことをしらざりけるに、實方の中將の教へ玉ひしより、はじめて花かづみといふものをふきたりけるにはまされど、いとひなびたり、多くの年月をへて逢たりし人々の、かはらぬ有さまに、桃柳ふきたる軒端の氣しきに、桃源の仙境に入しこゝろして
みなわかき顔見る桃の節句哉
| 蝶夢
|
此句にて一座あり、其夜より李山といふ人の別墅にうつりて、このころの旅心を慰む李山は橋野氏俗名要藏諱輝珍字忠如、線陰亭と號す、延享二年生文政十年歿、行年八十三歳
ある日、此裏山の吸江山に登る、江の中に出たる山也、めなれぬけしき多かる中にも、遠くは伊豫讃岐の山々横をれふし、近くは神武天皇の御船着たる神島、能登守教輕の合戦ありし水島をはじめ、鞆の津泉水山の島どもまで、なごりなくみゆ、かゝるながめあればにや、中むかし宗祇法師もこの浦山にて
山松のかげやうきみる夏の海
といふ發句ありしより、見るが岡といふ、爰に芭蕉翁の墳を築き一宇の草堂を建て、年月をへていまだ供養なかりしかば、其事すとて、六日ばかりがほど、此浦べにとどめられける。
十二日、あるじの老人とゝもに、田房の方へ行に、福田村雙三郡板木村字福田の長が家によりていこふに、かねて儲たりしにや、書院の飾より酒飯のもてなしまで、山里のさまなくて、つぎつぎし、硯料紙出して、物書よといふに、せんすべなくて
山里の風情そへたり蕗わらび
| 蝶夢
|
是より三次への間に、吉舎雙三郡吉舎といふ在名あり、後鳥羽院の隱岐へうつらせ玉ふ時、此里に宿らせ給ひて、よき舎りよと勅ありしより名とすとぞ、田房神石郡田總ちかくなりければ、越智何某梅下法師を伴ひて出迎ふ、此里にも芭蕉翁の碑を立けるが、けふしも忌日にあたれば、供養の俳諧を興行せんあらましにて、連衆の面々こゝの岨かげ、かしこの木のもとに、袴肩衣にて出迎ふたるは、にげなき心地ぞする、やがて臨川庵にて一座あり、かゝる山の奥までも、風雅の道の行わたりたる、翁の徳光のいたりなるべし、
十七日、日ほがらかなれば、此家を出立に、あるじも出雲の方見ざれば送らんとて、從者に物荷はせていず、今は四人になりければ、行先たのもし、家の内の男女、一里の老若おのおのどよみて見送るぞ、山里の風のいみじきなり。
門出のほだしや雨の蛙まで
| 古聲
|
けふは旅立なればと、はやくも實富といふ所の堀江氏が許に宿る。
よき家や門に青麥背戸に柴
| 蝶夢
|
廿三日、社人の案内にて御社にまうづ、此國の風土記に、八雲立と有しより、出雲とはよぶとか、その八雲山は社の後山也右に鶴山左に龜山あり、その八雲山ふところに宮柱ふとしく立しなり、地を杵築とは諸神地杵築玉ひて、宮を建しよりとぞ、神代記に高皇産靈尊、勅大己貴神曰、汝應住天日隅宮者以千尋栲繩結爲百二十紐其造宮之制者柱則高太板則廣厚、とあるごとく、材木なべてつぎはぎを用ず、ことごとく一木一枚なり神代には三十六丈なりしが、人の代となりて十六丈、今の世には八丈、床の高さ一丈二尺、巾六間四方に扉一口柱九本を以てたつ、檜皮をもつて葺き、千本かつほ木あり、普通の神社にたぐふべき所あらず、高樓のかたち希有の宮のかたち也、めぐりは瑞籬玉垣荒垣とて、三重にかこみ、其外觀祭樓廳屋拜殿等三ツ葉四ツ葉に作りみがゝれたり、かゝる波濤のすえに有べき結構にあらず、聞くよりは過てたふとく覺へけり、左に熊野川右に素鵞川流れて社をめぐる、誠に清地と神代よりいひつたへし事、いたづらならず、何事のおはしますとはしらず、六根清浄といふやうに、心すみぬ、法樂に
花といふ一字も神のめぐみかな
| 蝶夢
|
|
八雲山今見れば松のみどりたつ
| 同
|
|
春風や松よりうへは八雲たつ
| 古聲
|
|
中にこめて霞もふかし八雲山
| 沂風
|
平田平田町といふ所より便船ありければ、舟にのりて湖水宍道湖をわたる、夜すがら笘うちまといてねぶる、夜の明る比ほひ松江の橋の下につく、そもこの松江といふはこの江の鱸の巨口細鱗なる、もろこしの松江の鱸に似たれば湖水の名とせしとや、東西三里南北六里の大湖也、右に新隈、左は乃木濱、中に夜洲島ありて、美景いふべからず、城樓湖水に近く、市町湖水をかこみて、天府といふべき地勢なり、此町の長に小豆澤といふ人のもとへ尋けるに、饗膳に美を盡して日うつる、此人の父は常悦とて和歌の道に長ぜし人にて、都にも住て古きよしみなればなり、佐竹村の八重垣の社にまゐる、素盞烏尊稻田姫を祭る、八重垣とて社の中に柴垣をいくへともなう結廻したる所なり。
八重垣をめぐりめぐりて春くれぬ
| 蝶夢
|
|
八重垣にかさなる春の草木かな
| 古聲
|
青あらし淡路へも手のとゞくべし
| 蝶夢
|
|
すま寺や葉櫻くらう奥せまし
| 同
|
|
芦すだれ青くもかへす須磨の里
| 同
|
|
西すまやすだれにしらむ麥ほこり
| 古聲
|
五升庵蝶夢に戻る