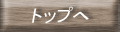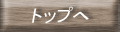上島鬼貫
『鬼貫句選』(太祇編)

明和5年(1768年)2月、不夜庵太祇序。
明和6年(1769年)1月、三菓軒蕪村跋。
元禄3年(1690年)9月20日、鬼貫は大坂を出て、10月2日に江戸に入る。想像上の旅だという。
人の親の烏追けり雀の子
鳥はまだ口もほどけず初ざくら
彌生降の雨を
春雨のけふばかりとて降にけり
京よりいたみへ行
水無月や風にふかれにふる里へ
此薄窓より吹や秋の風
富士の形は、畫るにいさゝかかは
る事なし。されども腰を帶たる雲
の今見しにはやかはり、其けしき
もまたまたおなじからずして、新
なる富士を見る事、暫時にいくば
くぞや。あし高山はおのれひとり
立なば並びなからん。外山の國に
名あるはあれど、古今景色のかわ
らぬこそあれ。
によほりと秋の空なる富士の山
禁足旅記
北窓の月は遠山の曉にそむき、南面の秋日は軒をめぐる事はやし。我レこゝろあらばめでたき閑居なるめれど、いやしければたのしみのおもひみじかく、欝寥たる秋の、中々吾妻のかたにたびしたけれど、用なきに身を遠く遊ぶ事、暫老親のためにおもひければ、こしかたに見つくしたる所々、居ながら再廻のまなこをおよぼし、日々こゝろばかりを脱けてゆかば、我願ひもたり、不孝にもあらずとおもひ立ぬ。
廿日の夕ぐれ大坂に出て、伏見への船かりてのる。
我が身に秋風寒し親ふたり
廿一日、ふしみにつく。朝ぼらけ打ながめ行に、町は所々家の隣、畠になりてさびし。
伏見人唐黍がらをたばねけり
別れて關の明神にまいる。
琵琶の音は月の鼠のかぶりけり
案内する子をやとひて、三井寺より高觀音にのぼる。所々の事念比に、夜は湖水の月など、舌さへまはらずいひしも、實(げに)馴ればおとなしき物をと愛らしくて、
大津の子お月様とはいはぬかな
松本を過てもころ川に至る。人の家のうしろに柿の木ありて、
義仲塚
柿葺や木曾が精進がうしにて
また膳所を行はなれて、秋の田の面の物あはれなる中に、
兼平塚
兼平が塚渺々とかり田かな
この所より道を右にのぼりて、
石山のいしの形もや秋の月
もどりに芭蕉がいほりにたづねて、
我レに喰せ椎の樹もあり夏木立
長はしをわたりて、
瀬田の秋よこ頬寒しかゞみやま
廿四日、桑名にいづ。風はげしくて船こはさに宿とる。座敷は海を請たる所なり。礒よりちいさき釣ぶねの行衛おぼつかなく見やりて、蛤など燒せてこゝろのびけり。
風の間に鱸(すずき)の鱠させにけり
午のさがりに風なをりて舟だす。うち晴てそこそこおもしろかりし物を、申のかしらより雨になりてういめす。漸日のおはるころ熱田にあがりて、こよひのやどかる。
熱田にて鱸(すずき)の鱠吐にけり
廿五日、なるみの宿をすぎて行さき、尾張・三河のさかひ橋あり。おはりのかた半は板をわたし、三河の地はつもりばしなり。
廿六日、ほどなくて御油の宿にかゝる。猶行道の左右に大きなる松はへつゞき、梢ひとつになりて、日の影さへもらぬほどなり。
たびの日はどこらにやある秋の空
よし田の町にて鶉きゝて、
うづら鳴吉田通れば二階から
ひうち坂といふ所に休て、
霧雨に屋ねよりおろす茶の木哉
ふた川を過行。爰にも三河・遠江の境に川橋あり。それを渡りて、
我裾は三河の露とまじりけり
白須賀こえて、荒井につく。濱名の橋のあとなつかしくて、
ことしにて濱名の橋は幾秋ぞ
また夜の心になりて
あの月やむかし濱名の橋の月
舟より前坂にあがりて、こよひは濱松に明す。
廿七日、天龍を渡る。
御上洛の御時は此橋舟橋になりぬと、船頭の物がたりす。げに宗苻が事を聞つたへて、なつかしくなりたり。
我祖父も舟橋おがむ秋の水
廿八日、小夜中山。
松杉のすげなふ立たる中に、朝日
影ちからなくさし入て猶心ぼそし。
けふともに秋三日あり小夜の山
江尻を過て、清見寺にのぼる。
庭上秋深うして佛閣靜に高し。海
原見やる所望めば、こゝろのび、
また心よはくなれり。
秋の日や浪に浮たる三穂の邊
興津の浦の海士の蚫とるなど、都にはなきをと見る。猶あら波のいそづたひに、道すなをならで、げに所の名もとおもふに、また古郷なつかしくて、
雜
故郷や猶こゝろぼそ親しらず
由井・かん原をこえて、富士川につく。色さへ余所の水にかはりて、船のさる事甚はやし。
不二川や目くるほしさに秋の空
よし原臥て晦日の朝、
秋の日や富士の手變の朝朗
うき嶋が原をひさしく通りて、
浮しまや露に香うつす馬の原
三しまの社を拜み奉るに、みな幾抱あらむとおもふ斗の松杉、間なく立こもりて、さびわたる神風に梢のしづく落るも遠し。眞砂はその白玉にうるほひ、御池は水の面青み立て、底おぼつかなくすごし。
雜
ちはやぶる苔のはへたる神鰻(※「魚」+「旦」)
のぼりのぼりて箱根のとうげにいたる。けふ三嶋の空にいたゞきたる雲ははるかなれど、こよひはまた其うへに枕す。
十月朔日、宿を出て行。俗にこの山にて死人にあふたる例おほしと、いひならはすほどに、
雜
水海や我影にあふ箱根やま
礒はたにさいの川原あり。念佛する法師の家、所々にきこえ、往來の人の小石あまた、つみかさねたるを見るにも、子をしたふ數しられてものあはれなり。
お地藏のもすそに鳴や礒鵆
權現にまいりて、
神の留守留守とおもへば神の留守
かしの木は皆人馬にものらず。そのほか岩根道いくまがりもまがりて、中々鈴鹿の坂はこの汗にも似ず。漸小田原にくだる。
雜
氣辛勞や馬にのろもの小田原へ
實(げに)こゝろばかり行道なれば、落る事もなきにと後悔してすぐ。曾我の里をとへば、海道とり十町ばかり左の山陰なりといふ。
さむ空にいとゞおもふや曾我の里
それより大磯にこえて、
とら御前今はつめたし石の肌
藤澤にとまりて、二日の朝遊行の御堂にまいる。看經の聲たふとく、我も無念の念佛す。
十月の二日も我もなかりけり
品川より鉄炮洲の御堂を見やりて、
むさしのは堂より出る冬の月
江戸に入て、日本橋を渡る。
いつもながら雪は降けり富士の山
嵐雪に行て宿す。去年の秋は、瓠界この庵に來て夜長く、ことしの春は、伴自が日永ふして我事いふにみじかく、また歸りていふに長し。たがひにわらつて夜もすがら兩吟す。句は其袋(※「代」+「巾」)にむかふ。
元禄三年庚午十月日
上島鬼貫に戻る