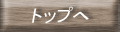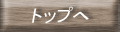高桑闌更

『半化坊発句集』(車蓋編)
半化坊は高桑闌更の別号。
天明7年(1787年)、刊。
風暁夢を破て、遊子関を越んと聞へしも、実や我半化翁も、其はじめは中比の風に遊び、加の浅野川の二夜庵に三とせあまり結びたる夢も、古調の為に破れ、終に深雪ふる越路に立出て
苦しさに休めば蚋のたかりけり
姨捨や石に置身も月のため
漏ざるをたのみぞ雪の薦かぶり
など風吟し客中に年を越て、霞たつ春は都の花にうかれ、ほとゝぎすの一声は淀の渡りに聞、月の清きには須磨の浦をたづね、橋立の詠には無季の格もしからんと、
橋立や守神なくば波越ん
かくいひ捨て、暫く此辺りになん周流せられける。とりが啼あづまの方もしたはるゝ折からは、甲信の音信に笠をかたぶけて、此間に年をかさね、ふたゝび武城に二夜庵をいとなみ、漂泊の労を養れけるが、例のうかれ心より、しらぬひの筑紫がた見まくほしと、又もや都にかへり給へば、したしき人々の杖をとり笠をかくすに任せ、市中に居をしめられしが、名利のさはりもあればと、東山にかくれて故翁の
柴の戸の月や其儘あみだ坊
と聞えしさびを「つぎて、南無庵の古しへを慕ひ、其地に芭蕉堂を結び、閑ならん事を願ふといへども、門人・遊子日々につどひ来り、閑居のいとまもなきに、うかれ神の立さらでや。
半化坊発句集 上
元日や此心にて世に居たし
山蔭や烟の中にむめの花
春もまだ雪にむなしき田面哉
堅田に至りて、故翁の吟をおもふ
病雁(やむかり)も残らで春の渚サかな
根をよけて火焚ケ桜に狂ふ人
はじめて花供養いとなみて
活て居て望の日の花備へけり
芭蕉堂にて
時なれや花の中なる翁堂
花戻り銭落したる坊主哉
山吹や終には流す花のかげ
川中島にて
川しまやつばな乱れて日は斜
桟谷亭を訪ふ
鳥啼て谷間も春の木立哉
夏
草津にて
六月やいたる所に温泉の流
温泉はあれど六月寒き深山哉
日光中禅寺
あら涼し四十八湖を渡る風
うらみの滝
ことによし裏みて潜る夏の滝
室の八しま
煙たへて久しき宮の茂り哉
親しらず
親しらば通さじ夏の海ながら
殺生河原
暑き日や蝶鳥落て石黄ミ
半化坊発句集 下
稲 妻
稲妻や静ならざる秋の空
夜田苅や明て休らふ身でもなし
今宵なれや月にむかふも月の上
阿漕が浦にて
月に猶哀あこぎが海の底
再び此浦に来りて
十六宵も月に阿漕はなかりけり
さし出の磯
黄昏や水にさし出のうす紅葉
酒折の宮もほどあらざれば
火ともしの神もめづらん月今宵
冬
冬木立
捨果し景色でもなし冬木立
枯芦の日に日に折て流れけり
神無月廿日あまり、故翁の湖東行
脚の跡を慕ひ、日野山の辺を過る
に、剥れたる身には砧の響哉 と
聞へ(え)しも今はむかしにて、目出度
御代のしるしなるにや。山も岡と
なり、林も畑とかはりて、しら波
の煩ひもなき折から、紫英亭にい
たりて、暫く時雨をはらす。
剥れざる身に冬しらぬ舎り哉
雑之部
日 光
日面も日うらも照らす宮居哉
善光寺
よごれたる我にも法の光りかな
杖突坂
歩行にせん杖突坂のためし有
高桑闌更に戻る