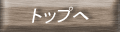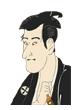
転寝の森〜阿部正方の歌碑〜


|
江戸時代後期の文化2年(1805年)に完成した白河の地誌『白河風土記』によれば、源義家が陸奥に下った際、林の下でしばらく休み、うたた寝をしたことからこの名がついたと伝える。 また『八雲集』にある清少納言曽弥の歌の「陸奥のうたたね(の)森のはしたへていなをふせとりもかよはさりけり」がこの場所であるという。 かつては森であったが、『白河風土記』が編纂される頃には杉が2本と桜の若木2株が残っているのみであったという。 根元の石碑には阿部正方の「いにしえのもの見の杉も跡たえて名のみぞのこるうたたねの森」の歌が刻まれている。
白河観光物産協会 |
|
○うたゝねの森、白河ノ近所、鹿島の社ノ近所。今ハ木一、二本有。 |
|
かしま成うたゝねの森橋たえていなをふせどりも通はざりけり(八雲ニ有由) |
|
うたたねの森はどこであろう。霧雨の中に探したがなかなか見当らない。ようやく探しあてたところは、青田の中に小さな楓と檜が見すてられたように立っているばかりだ。『奥州白河往昔記』に、八幡太郎吉家がこの森で憩うたのでこの名が起ったという。曾良は「今ハ木一、二本有」と書いているのだから、芭蕉のころも森の姿はなくなっていたのであろう。幅一メートルほどの用水が矢のように走っている辺を通って近づこうとしたが雨で滑るのでやめる。蕎麦の束を積んだ牛車がゆるゆると過ぎていった。 |

|
嘉永元年(1848年)8月21日、阿部正方は江戸に生まれる。 文久元年(1861年)、備後福山藩第9代藩主となる。 慶応3年(1867年)11月22日、没。 |