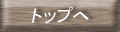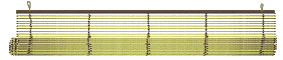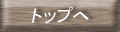私の旅日記〜2005年〜
葛飾八幡宮〜小林一茶の句碑〜
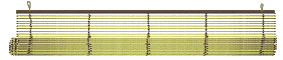
京成本線京成八幡駅北口を出て線路沿いに行くと、葛飾八幡宮がある。

参道を行くと、随神門の手前に小林一茶の句碑があった。

冬木立むかしむかしの音すなり
「なり」は断定ではなく、推定。
平成2年(1990年)4月、建立。
「葛飾を歩く会 万歩塚起点」と書いてあった。
葛飾八幡宮
寛平年間(889〜898)宇多天皇の勅願によって勧請された社で、古来武神として崇敬された。
御祭神は誉田別命(ほんだわけのみこと)(応神天皇)、息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)(神功皇后)、玉依姫命(たまよりひめのみこと)。
玉依姫命(たまよりひめのみこと)は海彦山彦の神話で知られる豊玉姫命の妹。
治承4年(1180年)源頼朝は安房国から下総国府へ入ると、自ら参詣して源氏の武運を祈願し、建久年間(1190〜1199)には千葉常胤(つねたね)に命じて社殿を修復させたという。
源頼朝公駒どめの石

頼朝公の馬がこの石に前足を掛け、ひづめの跡を残したことから、駒どめの石といわれる。
また、文明11年(1479年)太田道灌は臼井城の千葉孝胤を攻めるため、国府台に築城のさい、関東の安泰を祈って参拝し、社殿の修理を行った。更に天正19年(1591年)には、徳川家康が社領として朱印五十二石を供御(くぎょ)して崇敬している。
社殿

明治維新の神仏分離のときまでは、当宮境内にし上野東叡山寛永寺の末寺が別当寺として存在した。現存する鐘楼は往時を物語る貴重な遺物である。また、山門の仁王像は移されて、その後に左右両大臣像が置かれ、随神門とよばれるようになった。この随神門は市指定文化財である。
随神門

本殿の東側にそびえる「千本公孫樹(いちょう)」は天然記念物として国の指定を受け、また寛政5年(1793年)に発掘された元亨(げんこう)元年(1321年)在銘の梵鐘は県指定の文化財であり、梵鐘の銘文からも当宮創建の古さがうかがえる。
千本公孫樹(いちょう)

文化14年(1817年)8月27日、国学者高田与清は葛飾八幡宮のことを書いている。
八幡の里の八幡宮は、馬手(めで)の方の林中に在ておくまりたる宮居也。八幡宮は一宮・國分二寺・安國寺などやうにいづれの國にもありといへり。
文政8年(1825年)6月29日、渡辺崋山は行徳から葛飾八幡宮へ。
私の旅日記〜2005年〜に戻る