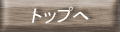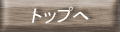新年の旅日記
善知鳥神社〜奥州街道終点記念の碑〜

青森市安方に善知鳥神社がある。

善知鳥神社
青森湊が開港以前の青森は「善知鳥村」と称して、安潟のほとりに漁家が点在する一漁村であった。
寛永時代に開かれた湊に寄せる漁船の目印が青々と茂る小高い森だったことから「青森」という名がついたという言い伝えがある。
善知鳥神社の創建については、坂上田村麿にゆかりがあるとも、都から移り住んだ烏頭中納言安方が宗像宮を祀ったともいわれるが、青森湊の開港後に再建されたようだ。
平安時代から現代にいたるまで多くの文化人・著名人が善知鳥神社について触れ、神社の由来、善知鳥という鳥、善知鳥にまつわる伝記、伝承について残している。
明治期、青森町の鎮守が毘沙門堂(香取神社)から善知鳥神社へ移された。神輿渡御も善知鳥神社が行うことになり、青森町の祭礼の中心となった。
鳥居の右手に「奥州街道終点記念の碑」があった。

平成3年(1991年)、建立。
東京日本橋が起点とされ、終点には諸説がある。江戸初期に著された「幕府撰慶長日本図」によると、津軽藩出張機関がおかれた青森市安方が終点とされている。
青い海公園へ。