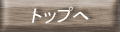青函連絡船戦災の碑
〜「津軽海峡冬景色」歌謡碑〜

私の旅日記〜2012年〜
青函連絡船戦災の碑
〜「津軽海峡冬景色」歌謡碑〜





| 上野発の 夜行列車 おりた時から |
| 青森駅は 雪の中 |
| 北へ帰る人の群れは 誰も無口で |
| 海鳴りだけを きいている |
| 私もひとり 連絡船に乗り |
| こごえそうな鴎見つめ |
| 泣いていました |
| ああ 津軽海峡 冬景色 |
| ごらんあれが竜飛岬 北のはずれと |
| 見知らぬ人が 指をさす |
| 息でくもる窓のガラス ふいてみたけど |
| はるかにかすみ 見えるだけ |
| さよならあなた 私は帰ります |
| 風の音が 胸をゆする |
| 泣けとばかりに |
| ああ 津軽海峡 冬景色 |
| さよならあなた 私は帰ります |
| 風の音が 胸をゆする |
| 泣けとばかりに |
| ああ 津軽海峡 冬景色 |