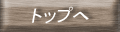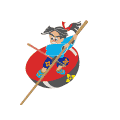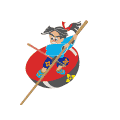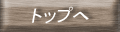今年の旅日記
ゴジラ岩〜塩瀬崎ジオサイト〜
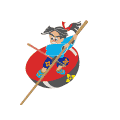
八望台から戸賀湾に下り、西海岸を行く。
カンカネ洞

下まで降りて行かなくてはいけないようだ。
西海岸ジオサイト
カンカネ洞
流紋岩の溶岩が波の侵食と土地の隆起によってえぐられてできた男鹿半島で最大の高さを誇る海食洞窟です。海、陸、空(天井)に穴が開いており、洞窟内は差し込む光と波の音でとても神秘的です。その昔、洞窟の絶壁に鉄のカギを掛けて上り下りしたことから「カギカケ」と言われ、それが変化して「カンカネ」と呼ばれるようになったと言われています。
文化7年(1810年)7月15日、菅江真澄は雁金(かんかね)の窟(いわや)に入ってみたが、暗くて奥まで行けなかった。
菅江真澄の道 蝙蝠の窟

蝙蝠の窟に漕ぎ寄せて、舵で船端をたたくと、その音に驚いて蝙蝠がむらむらと出てくるが、この中に五色の蝙蝠がいるという。それで五色の蝙蝠が五頭の鬼となったという伝説があるのだろうか。
舞台島

その昔、漢の武帝が降り立ち、巫女に舞を踊らせたという言い伝えが残されています。島という名ですが、実際には陸続きで、海面からの高さ約60mの平らな頂上部は、天空の舞台のようです。多くの絵図にも描かれており、江戸時代にはこの名で呼ばれていました。
舞台島は火山噴火によって生じた玄武岩質の岩石で構成されます。そして、波食台と呼ばれる、波に侵食された平らな地形になり、その後隆起したと考えられています。
文化7年(1810年)7月17日、菅江真澄は丸木舟で漕ぎ出して舞台島・蝙蝠の窟を訪れている。
塩瀬崎

男鹿半島・大潟ジオパーク
塩瀬崎
塩瀬崎ジオサイト
塩瀬崎は波に侵食された平らな地形(波食台)が少し隆起したものです。ここでは約3,000万年前の火山の噴出物である火山礫凝灰岩が風化によって独特の形に削り出されており、自然の美術館ともいえるジオサイトです。
ゴジラ岩

怪獣ゴジラにそっくりなことから、平成7年(1995年)に名付けられました。特に口元に夕陽と夕焼け雲を重ねた「火を吹くゴジラ」が人気です。
カメ岩

道路側から見ると、亀が海に向かっているように見えるので、「カメ岩」という名前が付きました。胴体が少し大きすぎてバランスはあまりよくありませんが、目を見張るほどの大きさがあります。甲羅の上には、昭和30年(1955年)に設置された潮瀬埼灯台が立っています。
鵜の崎海岸へ。
今年の旅日記に戻る