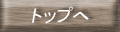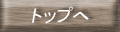私の旅日記〜2014年〜
小牧城〜小牧市歴史館〜

小牧市堀の内に小牧山がある。

史跡 小牧山
史跡小牧山は、永禄6年(1563年)に築かれた織田信長の居城小牧山城跡であり、天正12年(1584年)に徳川家康と豊臣秀吉が戦った小牧・長久手の合戦の古戦場でもあります。 標高85.6mの小山ですが、平野の中に独立してそびえる姿も美しく、山頂からは尾張平野を一望することができます。現在は、緑におおわれて市民の憩いの場でもあり、小牧市のシンボル的存在です。
歴史
永禄6年、織田信長は、清洲から小牧山に居城を移し、新しい尾張の政治経済の中心地として、城と城下町を整備しました。信長は、小牧山の山頂から麓まで、多数の曲輪を設けて、山全体を城としました。しかし、その4年後、信長は岐阜へ移り、小牧山城は廃城となり、城下町も衰えました。
信長が岐阜へ去った17年後の天正12年には、小牧・長久手の合戦が起こります。犬山から清洲をめざして攻め込もうとする豊臣秀吉の軍勢に対して、徳川家康と織田信雄の軍勢は、信長の城跡に、山麓を取り巻く堀や土塁を築くなどの大改造を行い、 堅固な城を築きました。 両軍は、にらみあいを続けましたが、小牧付近では大規模な合戦はおこらず、半年後には両軍ともに撤退し、小牧山城は、その後使われることはありませんでした。
江戸時代以降、尾張徳川家の保護などにより、小牧・長久手の合戦当時の城の遺構がよく残り、城郭史上の貴重な資料となっています。現在でも、山中に堀や土塁、曲輪などの跡を見ることができます。小牧山東麓には昭和22年に小牧中学校が建設されましたが、平成10年に移転して、その跡地は、発掘調査の成果に基づいて、主として小牧・長久手の合戦当時の姿に復元整備しましたが、部分的に織田信長の時代の屋敷跡を囲んでいた堀や井戸なども復元しています。
小牧城

小牧市歴史館である。
御嶽山(標高3,067m)がみえた。

「私の旅日記」〜2014年〜に戻る