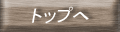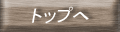私の旅日記
八坂神社〜元禄船着場跡〜

東彼杵町の彼杵神社から長崎街道を行くと、「元禄船着場跡」があった。

天明8年(1788年)3月23日、長月庵若翁は武雄・俵坂を越えて彼杵宿に入った。
其後旧遊親族追々に来て對して再會に驚き新謁に歓ふ、殊に我しらぬ孫ともの膝のもとにすりよりて、ものさへ得いハす只うち泪くミたるすかた、稚こゝにも何おもひけむ、いとあハれなり
むら雨に小百合なてし子うつふきぬ
『誹諧曇華嚢』
彼杵村から大村湾を望む景色

みなと公園 懐古の広場
徳川鎖國時代、長崎開港とともにここ彼杵の地は海陸交通の要路として栄えた宿場町であった。江戸〜長崎間を往来した幾多の先人たちが、この地にいこい、この港から時津に渡り長崎へ達したものである。
長崎県東彼杵町
「懐古の広場」に芭蕉の句碑があった。

華さかり山は日頃の朝ほらけ
出典は『芭蕉庵小文庫』。
「芳 野」と前書きがある。
貞亨5年(1688年)春、『笈の小文』の旅の折、吉野で詠まれた句。
八坂神社

八坂神社と祇園祭
この神社は祇園社として江戸時代の初めに創建されたと思われます。
その後、元禄7年(1694年)に開港した彼杵港の工事の時、現在のような社殿等が整備され、彼杵宿郷の氏神様として信仰されてきました。
江戸時代末期、シーボルトが江戸参府のため彼杵宿に宿泊した時、絵師に描かせた彼杵港の絵にこの神社も描かれています。鳥居は寛政12年(1800年)に建てられ、明治3年(1870年)に八坂神社に改称されました。
祭神はインドの祇園精舎の守護神牛頭天王(ごずてんのう)で、日本での神様は素戔嗚尊(すさのおのみこと)とされ、疫病除けの神として尊びあがめられています。
現在でもその願いをこめて本町・金谷・東町が輪番で踊り町となり、ときおり県指定の坂本浮立や蔵本浮立も出て、7月下旬に氏子により祇園祭が行われています。
昔からこの地域では一番の華やかでにぎやかな祭りです。
彼杵宿街道まちおこし隊
明和8年(1771年)5月、蝶夢は彼杵から大村城下へ。
薗木の浦は入江ひろく、嶋山つらなりて景致なり。大村の城下に坡明といふものを尋るに、悦びなのめならず。くだ物取ちらしてちそうす。此あたりは疱瘡をやむものあれば、ふかくいとひにくみて最愛の子といへども、遙なる山の中に捨置べき国の法なりとぞ。まさしく此家の次郎なるわらはべもさし侍るとかたる。
文化2年(1805年)10月11日、太田南畝は彼杵で昼休みする。
小流をわたり濱づたひしてめぐりゆくに、川あり飛石午の時彼杵(カノキ)の晝休につく。こゝにいたりて、長崎のかたを見やるに、時津のむかひなるべし。
『小春紀行』
文政6年(1823年)、シーボルトはオランダ商館の医師として長崎にきた。
文政9年(1826年)2月16日、江戸参府紀行のおり彼杵「庄屋」に泊まった。
嘉永3年(1850年)9月3日、吉田松陰は長崎に遊学する途中で彼杵に至る。
坂を下れば冑山甲田あり、左に見て過ぐ。彼杵に至れば斜日一竿。
「私の旅日記」のトップページへ