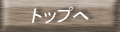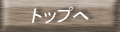私の旅日記〜2004年〜
鑁阿寺〜『徒然草』の碑〜

三毳山から両毛線に沿って県道67号桐生岩舟線を行き、足利学校に向かう。
足利学校に行く前に、鑁阿寺(ばんなじ)に立ち寄る。

鑁阿寺は真言宗大日派の寺。
関東八十八ヵ所霊場第16番札所である。
源義家の三男義国は下野国足利郡(現栃木県足利市)を伝領。義国の長男義重は上野国新田郡(現群馬県太田市)を譲られ、新田氏を名乗る。二男義康の子孫は足利氏を名乗る。
義康の三男義兼は、源頼朝に仕える。
義兼の妻は頼朝の妻北条政子(1156−1225)の妹時子。
建久6年(1195年)3月12日、足利義兼は東大寺で出家、法名を鑁阿房義称と称する。
建久7年(1196年)、義兼が邸内に大日如来を安置。
これが鑁阿寺の始まりとされる。
鑁阿寺経堂

応永14年(1407年)、関東管領足利満兼により再建された。
昭和59年(1984年)、国重要文化財に指定。
永正6年(1509年)、柴屋軒宗長は鑁阿寺を訪れている。
御当家の旧跡鑁阿寺一見して、千手院といふ坊にして、茶などのついでに、今夜はここにとしひてありしに、この院主、もと草津にて見し人なり。かたがた辞しがたくて、三日ばかりあり。
大御堂(大日堂)

本尊は大日如来。
天保2年(1831年)10月22日、渡辺崋山は足利学校を出て、鑁阿寺へ。
出て担角清風楼といえるにいざなはる。途に大日如来の堂あり。これなんいと霊場にて街の東にあり。喬木森然として奥に大日の伽藍あり。むねハ雲にそびふるばかり高くひろくて、わたり堂、二王門、三層浮図、経堂、裏門二、誠に荘厳といふべきなり。
『徒然草』(第216段)の碑があった。

最明寺入道は鎌倉幕府5代執権北条時頼のこと。時頼は康元元年(1256年)11月23日出家し、最明寺殿と呼ばれた。鶴岡(つるがをか)は鶴岡八幡宮。足利左馬入道は足利義兼の子、義氏のこと。隆弁僧正は四条大納言隆房卿の子。権僧正。
他にも碑があったが、説明がないので、わからない。
鑁阿寺鐘楼

建久7年(1196年)、足利義兼建立。
昭和26年(1951年)、国重要文化財に指定。
木蓮が咲いていた。

木蓮はモクレン科。
木瓜(ぼけ)

木瓜(ぼけ)はバラ科の花。
土塁と水堀

桜には少し早い。
鑁阿寺は「足利氏宅跡(鑁阿寺)」として国の史跡に指定されている。
日本100名城の一つだそうだ。知らなかった。
足利学校へ。
「私の旅日記」〜2004年〜に戻る